今回はクロモ山南尾根を登り、クロモ山北尾根を下ります。そうです。いったん完結した『大丹波川(おおたばがわ)左岸・名も無き尾根シリーズ』の復活編です。大丹波川上流域からクロモ山に登り、長沢背稜を乗り越そうというルートです。クロモ山の位置は下の地図を参照してください。
概略は、JR青梅線川井駅をスタートして大丹波林道をえんえんと歩き、クロモ山で東京都奥多摩町から埼玉県飯能市へまたぎ、有馬林道に降りてえんえんと歩き、名栗湖の左岸(北面)もえんえんと歩き、ゴールにむふふのさわらびの湯を見据えた尾根歩きです。
梅雨明け第1弾にふさわしい天晴な(※個人の感想です)計画だったんですが、クロモ山からの尾根間違いに落とし物、ココロにはほろ苦い薄雲が立ちこめたのでした。
※「標高」は省略しています。
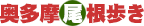
クロモ山南尾根、クロモ山北尾根(下半分)
(1/2)
| ■コース | [START]JR青梅線川井駅→(1時間15分)朴橋→大丹波林道→(1時間10分)クロモ山南尾根取付→クロモ山南尾根→(2時間40分)クロモ山→長沢背稜→(35分)クロモ山北尾根(下半分)→(35分)オハヤシ沢→(5分)有馬林道→有間渓谷観光釣場→名栗湖左岸道路→竜神の湧水→有間ダム→(1時間50分)[GOAL]さわらびの湯→ノーラ名栗・さわらびの湯バス停→西武池袋線飯能駅 (8時間10分) |
| ■歩いた日 | 2025年7月19日(土) |
※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。
■[START]JR青梅線川井駅→(1時間15分)朴橋→大丹波林道→(1時間10分)クロモ山南尾根取付→クロモ山南尾根→(2時間40分)クロモ山
クロモ山南尾根は取付がはっきりしないままの出発でした。Googleマップのストリートビューの範囲外だし、航空写真を拡大してもどこから取付けるのかさっぱり見当がつきません。現場で探すしかありませんでした。
忘れていました。『大丹波川左岸・名も無き尾根シリーズ』の尾根は800m〜900mあたりに岩崖ゾーンが仕込まれています。クロモ山南尾根も短いけれど岩崖ゾーンをしっかり隠し持っていて、山ノ神尾根ほどではないけれど小怒田ノ尾根の2.1ランク上くらいのとんでもないキビシさとデンジャラスな這い上がりに泣きそうになりました。
 おはようございます。JR立川駅でダンディ髭のSさんとばったり会って、降車駅も同じ川井駅でした。あーだこーだと話ながら川井駅から大丹波川沿いを歩き、逆川左岸尾根を登るというSさんと小山(こやま)バス停の階段でわかれ、ちょっと不気味に感じるヤマユリを愛で、
おはようございます。JR立川駅でダンディ髭のSさんとばったり会って、降車駅も同じ川井駅でした。あーだこーだと話ながら川井駅から大丹波川沿いを歩き、逆川左岸尾根を登るというSさんと小山(こやま)バス停の階段でわかれ、ちょっと不気味に感じるヤマユリを愛で、 百軒茶屋の四等三角点(標高 405.46m、基準点名は奥中茶屋)を擁壁の上に見て、
百軒茶屋の四等三角点(標高 405.46m、基準点名は奥中茶屋)を擁壁の上に見て、 「黒山・棒ノ折山」の登山道を過ぎ、
「黒山・棒ノ折山」の登山道を過ぎ、 朴橋(ほうのきはし)を渡って大丹波林道に踏み入ります。正面は笹野沢右岸尾根です。
朴橋(ほうのきはし)を渡って大丹波林道に踏み入ります。正面は笹野沢右岸尾根です。 槙乃尾橋(まきのおはし)を渡ります。槙ノ尾山南尾根や槙ノ尾沢左俣右岸尾根の激登が思い出されます。すみません、ちょっとウソです。あまり覚えていません。
槙乃尾橋(まきのおはし)を渡ります。槙ノ尾山南尾根や槙ノ尾沢左俣右岸尾根の激登が思い出されます。すみません、ちょっとウソです。あまり覚えていません。 新秩父線44号鉄塔尾根の取付への下降点です。堰堤工事のためのモノレールの駅が設置されていたんですが(「新蔵指ノ丸北東尾根、曲り尾根」)きれいさっぱりなにもなかったように撤収されています。
新秩父線44号鉄塔尾根の取付への下降点です。堰堤工事のためのモノレールの駅が設置されていたんですが(「新蔵指ノ丸北東尾根、曲り尾根」)きれいさっぱりなにもなかったように撤収されています。 大丹波ヘリポートを過ぎ、
大丹波ヘリポートを過ぎ、 大丹波川へのひとつめの下降点を過ぎ、
大丹波川へのひとつめの下降点を過ぎ、 ふたつめの下降点を過ぎ、
ふたつめの下降点を過ぎ、 『奥多摩 登山詳細図(東編)』(吉備人出版)にイワ沢と表記されている沢の左岸に「おいでおいで」している踏み跡があったんですがここからクロモ山南尾根はちょっと遠いです。
『奥多摩 登山詳細図(東編)』(吉備人出版)にイワ沢と表記されている沢の左岸に「おいでおいで」している踏み跡があったんですがここからクロモ山南尾根はちょっと遠いです。 不法投棄された自転車やブラウン管テレビを過ぎ、
不法投棄された自転車やブラウン管テレビを過ぎ、 このあたりがなんとなく取付きに想定していた場所です。名前のわからない小さな沢の左岸です。うーん、樹木の勢いが強すぎます。さらに先に進んで取付けそうな場所を探してみたんですが崖だらけで戻ってきました。
このあたりがなんとなく取付きに想定していた場所です。名前のわからない小さな沢の左岸です。うーん、樹木の勢いが強すぎます。さらに先に進んで取付けそうな場所を探してみたんですが崖だらけで戻ってきました。ザックを降ろし、軍手、杖を引っ張り出し、首にかけていた手ぬぐいをしごいて正装に。ペットボトルに詰めてきたほうじ茶を一口飲んでクロモ山南尾根に取付きます。
 藪を突っ切って尾根下端の横っ腹を登ってきました。写真中央やや上が林道です。小焼山北尾根で今年分の藪こぎは終わったはずですが、そんなに甘くはありませんでした。
藪を突っ切って尾根下端の横っ腹を登ってきました。写真中央やや上が林道です。小焼山北尾根で今年分の藪こぎは終わったはずですが、そんなに甘くはありませんでした。 藪を抜けるとクロモ山南尾根の稜線が見えてきました。
藪を抜けるとクロモ山南尾根の稜線が見えてきました。 クロモ山南尾根に立ちました。大丹波川の対岸に曲ヶ谷沢左岸尾根が見えています。
クロモ山南尾根に立ちました。大丹波川の対岸に曲ヶ谷沢左岸尾根が見えています。 大丹波川(林道)に落ち込んだ尾根下端。
大丹波川(林道)に落ち込んだ尾根下端。 足元の右は崩落地のてっぺんです。大丹波林道の末端とその手前に大きな崩落地がありますが末端手前の崩落地です。えぐれています。長居は無用です。振り向いて
足元の右は崩落地のてっぺんです。大丹波林道の末端とその手前に大きな崩落地がありますが末端手前の崩落地です。えぐれています。長居は無用です。振り向いて ややヤセた急勾配を登ります。
ややヤセた急勾配を登ります。 ワイヤーを通過します。
ワイヤーを通過します。 ゴーロ、ガレ、ザレを順番に登っていくと
ゴーロ、ガレ、ザレを順番に登っていくと 岩崖にぶつかりました。870m圏です。
岩崖にぶつかりました。870m圏です。 右から
右から 左まで尾根を完全にふさいでいます。左に回り込む薄い踏み跡があるようなないような。けれども急斜面ののっぺりトラバース(山腹水平移動)です。
左まで尾根を完全にふさいでいます。左に回り込む薄い踏み跡があるようなないような。けれども急斜面ののっぺりトラバース(山腹水平移動)です。 正面やや右の崖に取付くことにしました。あそこなら登れそうです。
正面やや右の崖に取付くことにしました。あそこなら登れそうです。 近づいていくと驚いたことに朽ちかけた木に朽ちかけた1mちょっとほどのロープがぶら下がっていました。ただ、このロープを使ってどうすればいいのかわかりません。右に移動し、岩をつかみながら這い上がります。
近づいていくと驚いたことに朽ちかけた木に朽ちかけた1mちょっとほどのロープがぶら下がっていました。ただ、このロープを使ってどうすればいいのかわかりません。右に移動し、岩をつかみながら這い上がります。 這い上がってきました。前の写真から20分ほどたっています。つかんだ岩の角はボロボロガクガク取れるし写真なんか撮っていると命を取られそうな崖がつづきました。木の幹とルーツファインディング(登攀を支持する木の根を探ること)が頼りです。
這い上がってきました。前の写真から20分ほどたっています。つかんだ岩の角はボロボロガクガク取れるし写真なんか撮っていると命を取られそうな崖がつづきました。木の幹とルーツファインディング(登攀を支持する木の根を探ること)が頼りです。 岩に背を付けて休憩します。高級食材とされるイワタケも岩にへばり付いています。採っている余裕なんてございません。
岩に背を付けて休憩します。高級食材とされるイワタケも岩にへばり付いています。採っている余裕なんてございません。 這い上がってきて
這い上がってきて 910m圏でまた休憩です。身もココロも消耗します。ザックを降ろすと転げ落ちそうです。背負ったまま岩の上に体育座りでペットボトルに詰めてきたほうじ茶をごくごくと飲みます。
910m圏でまた休憩です。身もココロも消耗します。ザックを降ろすと転げ落ちそうです。背負ったまま岩の上に体育座りでペットボトルに詰めてきたほうじ茶をごくごくと飲みます。 行く手を見上げます。まだまだ這い上がりがつづきそうです。
行く手を見上げます。まだまだ這い上がりがつづきそうです。 這い上がってきて
這い上がってきて また岩崖です。
また岩崖です。 這い上がってきて
這い上がってきて 940m圏でまた休憩です。どうやらようやく岩崖ゾーンは終わったみたい。ザックを降ろします。
940m圏でまた休憩です。どうやらようやく岩崖ゾーンは終わったみたい。ザックを降ろします。 尾根歩き再開。地形図ではわかりませんが尾根は二俣にはっきりわかれていました。左から登ってきた尾根と合流します。こちらと同じく急峻な尾根です。
尾根歩き再開。地形図ではわかりませんが尾根は二俣にはっきりわかれていました。左から登ってきた尾根と合流します。こちらと同じく急峻な尾根です。 左の尾根の突き出た岩が見えてきました。行ってみます。
左の尾根の突き出た岩が見えてきました。行ってみます。 崖上に立ちました。うーむ、バーンと開けているかと思ったけれどそうでもありませんでした。980m圏です。
崖上に立ちました。うーむ、バーンと開けているかと思ったけれどそうでもありませんでした。980m圏です。 大丹波川の上流方向です。ひょっとして正面奥は川苔山?
大丹波川の上流方向です。ひょっとして正面奥は川苔山? 川苔山? に背を向け登ります。尾根相はすっかり変わり、ヒノキの植林に囲まれました。
川苔山? に背を向け登ります。尾根相はすっかり変わり、ヒノキの植林に囲まれました。 登ってきて
登ってきて 尾根は絞られ
尾根は絞られ 長沢背稜の南面の巻き道を横断します。
長沢背稜の南面の巻き道を横断します。 長沢背稜上の小ピークに立ったんですが、クロモ山はもう少し左(西)です。
長沢背稜上の小ピークに立ったんですが、クロモ山はもう少し左(西)です。 小ピークを下って登ってクロモ山の山頂(1040m圏)に到着。これにてクロモ山南尾根はおしまいです。
小ピークを下って登ってクロモ山の山頂(1040m圏)に到着。これにてクロモ山南尾根はおしまいです。クロモ山は漢字で書くと黒椴山らしい。椴はトドマツのことでトドマツといえば生えているのは北海道だと思うんですが、謎の山名です。
つづいてクロモ山北尾根を下ります。が、クロモ山南尾根の激登を終えたせいか油断していました。
大丹波川林道から長沢背稜のクロモ山までクロモ山南尾根を登った映像です。