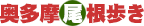
愛宕尾根、(山内新四国八十八ヶ所霊場)
(2/2)
■山内新四国八十八ヵ所札所霊場→(1時間30分)展望台(幸せの鐘)→(10分)愛宕尾根→(10分)愛宕山(奥の院)→愛宕尾根通行止地点→作業場
八十八ヶ所札所巡りの遍路を終え、幸せの鐘の展望台で鐘を鳴らしました。愛宕尾根に乗り、もうすぐ三室山(みむろやま)というところで通行禁止のテープがビシッと張らていました。ビシッと。空中のワイヤーロープが低く重く唸り、尾根の西側で伐採した木を東側に降ろしています。1本吊りされた木が尾根上を越えていきます。作業中でなければそのまま稜線を登るところですが、この状況は自己責任という問題ではありません。万が一のときは四方八方あらゆるところに迷惑をかけてしまします。
スマホGPSで打開策を練ります。前回につづいてまた撤退の憂き目は避けたいところです。
 八十八番札所を出発してゆるく登っていくと「幸せの鐘 展望台」の道標がありました。立ち寄ってみます。
八十八番札所を出発してゆるく登っていくと「幸せの鐘 展望台」の道標がありました。立ち寄ってみます。 道標からゆるく下ってすぐ、「幸せの鐘 展望台」に着きました。460mあたりです。
道標からゆるく下ってすぐ、「幸せの鐘 展望台」に着きました。460mあたりです。 鐘の鳴らし方は「1打目はそっと自分のために 2打目は心を込めて大切な人のために 3打目は大きくみんなのために」。初めてなもので力加減がわからず1打目から大きくいってしまいました。2打目、3打目は自分でもうるさかったです。
鐘の鳴らし方は「1打目はそっと自分のために 2打目は心を込めて大切な人のために 3打目は大きくみんなのために」。初めてなもので力加減がわからず1打目から大きくいってしまいました。2打目、3打目は自分でもうるさかったです。 梅郷(ばいごう)の皆様、お騒がせしました。蛇行する多摩川の下流方向がずーっと見え、シャープペンの芯のような東京スカイツリーも見えました。
梅郷(ばいごう)の皆様、お騒がせしました。蛇行する多摩川の下流方向がずーっと見え、シャープペンの芯のような東京スカイツリーも見えました。 右手上方、見えない写真の外に愛宕尾根が走っています。
右手上方、見えない写真の外に愛宕尾根が走っています。 眺望を堪能し、愛宕尾根の稜線をめざします。新所沢線27号の鉄塔を右手に通過し、
眺望を堪能し、愛宕尾根の稜線をめざします。新所沢線27号の鉄塔を右手に通過し、 すぐの分岐です。新所沢線26号は左、わたくしは右へ。
すぐの分岐です。新所沢線26号は左、わたくしは右へ。 マダニが潜んでいそうな草ボーボーゾーンを抜け、
マダニが潜んでいそうな草ボーボーゾーンを抜け、 「アタゴ尾根コース」の案内板です。左に曲がる踏み跡が濃いんですが、正面奥に愛宕尾根の稜線が見えています。そのまま直進します。
「アタゴ尾根コース」の案内板です。左に曲がる踏み跡が濃いんですが、正面奥に愛宕尾根の稜線が見えています。そのまま直進します。 左からゆるーく登ってきて愛宕尾根に立ちました。尾根上を登ります。
左からゆるーく登ってきて愛宕尾根に立ちました。尾根上を登ります。 しばらく薄い踏み跡だったんですが、やがてしっかりした登山道に合流しました。案内板から左に折れるた道でしょう。快適な尾根歩きです。
しばらく薄い踏み跡だったんですが、やがてしっかりした登山道に合流しました。案内板から左に折れるた道でしょう。快適な尾根歩きです。 愛宕山の山頂直下の登りです。
愛宕山の山頂直下の登りです。 「十八丁目 二俣尾 市川某 峯岸某」と彫られた石柱が立っていて
「十八丁目 二俣尾 市川某 峯岸某」と彫られた石柱が立っていて 愛宕山山頂に建立されている愛宕神社奥の院に到着です。石段をあがり、
愛宕山山頂に建立されている愛宕神社奥の院に到着です。石段をあがり、 本堂です。「愛宕神社」と金文字で彫られた扁額が掛けられています。
本堂です。「愛宕神社」と金文字で彫られた扁額が掛けられています。 広い境内の左奥に安置されている石像は役小角(えんのおづぬ)という実在したのかよくわからない飛鳥時代の呪術者らしい。修験道の基礎をつくり、鬼の夫婦を弟子にしていた、冤罪で伊豆大島に流されたときは昼は伊豆にいて夜は富士山で修行していた、などの伝承がある不可思議な怪人です。石像の近辺に584mの標高点が設定されています。
広い境内の左奥に安置されている石像は役小角(えんのおづぬ)という実在したのかよくわからない飛鳥時代の呪術者らしい。修験道の基礎をつくり、鬼の夫婦を弟子にしていた、冤罪で伊豆大島に流されたときは昼は伊豆にいて夜は富士山で修行していた、などの伝承がある不可思議な怪人です。石像の近辺に584mの標高点が設定されています。 愛宕神社を辞し、愛宕山の山頂からぐーっと下っていき、
愛宕神社を辞し、愛宕山の山頂からぐーっと下っていき、 鞍部から登っていくと「伐採作業中につき 立入禁止 伐採木や岩石の飛来あり、命の危険あり」と書かれた看板が立っていました。560m圏です。周囲の雰囲気に固い意志が感じられます。木の幹の立入禁止区域を示したポスターは麓の愛宕神社あたりで見た気がます。わたくしには関係ないもの、と思い込んでいましたが、ガッツリとビシッと関係がありました。困りました。とっても困りました。(作業は8月13日終了予定)
鞍部から登っていくと「伐採作業中につき 立入禁止 伐採木や岩石の飛来あり、命の危険あり」と書かれた看板が立っていました。560m圏です。周囲の雰囲気に固い意志が感じられます。木の幹の立入禁止区域を示したポスターは麓の愛宕神社あたりで見た気がます。わたくしには関係ないもの、と思い込んでいましたが、ガッツリとビシッと関係がありました。困りました。とっても困りました。(作業は8月13日終了予定) 伐採が行われているのは稜線の東面(左)です。空中高くにワイヤーロープが張られています。ワイヤーロープに滑車がぶら下がっていて低く唸りながら稜線右から左へ越えていくのが見えます。スマホGPSを引っ張り出し、ほうじ茶を飲みながらあーでもないこーでもないと進路を考えます。右手下からチェーンソーの音がせり上がってきます。前回につづいての撤退は避けたいところです。またワイヤーロープが唸り、今度は左から右へ滑車の下に吊り下げられた伐採木が稜線を越えていきます。決めました。伐採作業の行われていない西面をトラバース(山腹水平移動)して伐採ゾーンを巻くことにします。
伐採が行われているのは稜線の東面(左)です。空中高くにワイヤーロープが張られています。ワイヤーロープに滑車がぶら下がっていて低く唸りながら稜線右から左へ越えていくのが見えます。スマホGPSを引っ張り出し、ほうじ茶を飲みながらあーでもないこーでもないと進路を考えます。右手下からチェーンソーの音がせり上がってきます。前回につづいての撤退は避けたいところです。またワイヤーロープが唸り、今度は左から右へ滑車の下に吊り下げられた伐採木が稜線を越えていきます。決めました。伐採作業の行われていない西面をトラバース(山腹水平移動)して伐採ゾーンを巻くことにします。 獣かヒトか両方か、踏み跡らしきものがあります。たどります。
獣かヒトか両方か、踏み跡らしきものがあります。たどります。 できるだけ稜線からはなれたくないんですが、
できるだけ稜線からはなれたくないんですが、 そうもいかず、歩きやすそうなルートを探っていくとかなり下っていったりもします。シンドいトラバースがつづきます。
そうもいかず、歩きやすそうなルートを探っていくとかなり下っていったりもします。シンドいトラバースがつづきます。 僥倖です。しっかりした作業道にぶつかりました。
僥倖です。しっかりした作業道にぶつかりました。 ぐんぐん進みます。
ぐんぐん進みます。 分岐です。しっかりした道は小尾根を縫うように下っていきます。ずーっと下には林道が見えています。けれども下るわけにはいきません。ちょっと危ういけれど
分岐です。しっかりした道は小尾根を縫うように下っていきます。ずーっと下には林道が見えています。けれども下るわけにはいきません。ちょっと危ういけれど トラバースをつづけます。途中、2〜3mの高さにある弛んだり張ったりするワイヤーロープくぐったりもしました。架線を使った集材の仕組みは素人にはよくわかりません。
トラバースをつづけます。途中、2〜3mの高さにある弛んだり張ったりするワイヤーロープくぐったりもしました。架線を使った集材の仕組みは素人にはよくわかりません。 まだ伐採地を抜けられませんが、トラバースはかなりデンジャラスな様相を呈してきました。さらにキビシい事実が判明。この先、小さな谷と尾根の先で伐採木が山肌を擦るように林道に向かって降ろされています。そんなところを横断できません。無理。急斜面に足を踏ん張ってスマホGPSで打開策を探ります。決めました。林道に降りて作業現場を通らせてもらうようお願いしてみます。作業現場を抜け、明王沢という沢沿いにある林道を詰めていけば三室山にごく近い愛宕尾根に登れるはずです。先ほどの林道が見えた分岐まで引き返します。
まだ伐採地を抜けられませんが、トラバースはかなりデンジャラスな様相を呈してきました。さらにキビシい事実が判明。この先、小さな谷と尾根の先で伐採木が山肌を擦るように林道に向かって降ろされています。そんなところを横断できません。無理。急斜面に足を踏ん張ってスマホGPSで打開策を探ります。決めました。林道に降りて作業現場を通らせてもらうようお願いしてみます。作業現場を抜け、明王沢という沢沿いにある林道を詰めていけば三室山にごく近い愛宕尾根に登れるはずです。先ほどの林道が見えた分岐まで引き返します。 林道のむこうの山腹にシカがいました。この写真に少なくとも4頭いて、1頭はじーーっとこちらを見ています(円内)。
林道のむこうの山腹にシカがいました。この写真に少なくとも4頭いて、1頭はじーーっとこちらを見ています(円内)。 分岐から小尾根を下ってきました。踏み跡は自然消失。
分岐から小尾根を下ってきました。踏み跡は自然消失。 テキトーに下ってきて
テキトーに下ってきて 擁壁が低くなっているところから
擁壁が低くなっているところから 林道に降りました。伐採木がくーっと下っています。チェーンソーの音がする現場に向かってゆるく登っていきます。
林道に降りました。伐採木がくーっと下っています。チェーンソーの音がする現場に向かってゆるく登っていきます。 伐採木の集積場です。ワイヤーロープを操作するウインチが据えられ、伐採木をつかんで運ぶグラップル(積まれた材木の上、左端にちょっぴり見えています)が首を振りながら動き回っています。右奥ではチェーンソーを持った作業員が運ばれてきた伐採木を切りそろえようとしています。
伐採木の集積場です。ワイヤーロープを操作するウインチが据えられ、伐採木をつかんで運ぶグラップル(積まれた材木の上、左端にちょっぴり見えています)が首を振りながら動き回っています。右奥ではチェーンソーを持った作業員が運ばれてきた伐採木を切りそろえようとしています。作業員の方たちと話しました。こころよく通させていただきました。ありがたいことです。三室山までのおおよそのルートも教えてもらえました。作業が一区切りつくまで待ちます。積まれている木はヒノキで柱になるそう。
撤退せずにすんだのはいいけれど、ここから愛宕尾根までがとんでもなくツラい激登になってしまいました。つづきは後編「松尾沢左岸尾根」へ。