遠征です。遠征続きです。今回は秩父の立橋尾根(たてはしおね)を登り、矢岳尾根の赤岩ノ頭と矢岳の間から作業道を秩父林道の終点まて下り、秩父林道、秩父併用林道を武州日野駅まで歩きました。
立橋尾根のてっぺんは長沢背稜の日向谷ノ頭から矢岳に連なる矢岳尾根にある立橋山、と言いたいところですが、実は立橋山の位置がはっきりしません。地図を見る限り、立橋尾根のてっぺんは標高1530m圏(以降、「標高」は省略)のピークですが、『ヤマレコ』や『YAMAP』、『ヤマケイオンライン』の圧倒的多数の投稿が1568mの標高点を立橋山としています。『ヤマレコ』の立橋尾根を登った記録が1530m圏のピークを旧立橋山と称して、立橋尾根のてっぺんとした記録があります。かと思えば『山と高原地図 奥武蔵・秩父』(昭文社)にはこの旧立橋山の位置に立橋山の名前が記載されていて、この立橋山から北西に向かって立橋尾根の文字がビシッと掲載されています。場所確定の綱引きがされている最中なのでしょうか。謎です。本文でも触れますが『奥多摩』(宮内敏雄 著 昭和刊行会 刊 昭和19)の地図では1530m圏のピークを立橋山と記載しているように見えます。
尾根にてっぺんの名前がないと話を進めづらいので、立橋尾根のてっぺんは旧立橋山ということにします。
ということで、立橋尾根は旧立橋山から北西に下り、安谷川(あんやがわ 川浦谷渓谷)の上流部に架かる秩父橋あたりに没しています。 立橋尾根の肝は序盤の岩登りです。下調べの情報に違わずそれはもうとてもキビシいものでした。
下りは矢岳北尾根を歩こうと思っていたんですが、立橋尾根の岩登りにやられまくれ、どう見積もっても山中で日没を迎えて真っ暗になりそう。そこでエスケープルート(いざというときの逃げ道)としてなんとなく地図に書き込んでいた赤岩ノ頭というピークと矢岳の間にある荒川分岐から秩父林道の終点を目指すことにしました。林道なら真っ暗になってもヘッドランプを点ければ危険は少ないだろうという判断だったんですが、このエスケープルートは逃げているのか突入しているのかわからなくなるほどなかなかキビシい道でした。
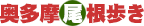
立橋尾根
(1/2)
| ■コース | [START]秩父鉄道武州日野駅→秩父林道→(1時間40分)秩父橋→立橋尾根→(3時間10分)1183m標高点→(1時間40分)旧立橋山→赤岩ノ頭→(35分)荒川分岐→作業道→(1時間)秩父林道終点→道間違い→秩父林道→(2時間10分)[GOAL]秩父鉄道武州日野駅 (10時間15分) |
| ■歩いた日 | 2022年10月15日(土) |
※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。
■[START]秩父鉄道武州日野駅→秩父林道→(1時間40分)秩父橋→立橋尾根→(3時間10分)1183m標高点
立橋尾根に取付いて10数分後の岩崖(がんがい 岩でできた急斜面をいい、原則として高さ5m以上かつ長さ図上2cm以上のものに適用し、それより小規模のものは必要に応じて表示しています。 以上、国土地理院のサイトより引用)は左に巻いた、つもりでしたがほぼ匍匐前進みたいな場所もあったりする激登でした。おそらく巻きが足りなかったんだと思います。キビシい急登がちょっと続いた先の次なる岩崖は右に巻きました。またキビシい急登がしばらく続いて標高920m(以降、「標高」は省略)あたりのガッツリした岩崖は直登して途中から右に回り込んだんですが断崖の上に出て驚愕。引き返し、左に巻いててっぺんへ。序盤の3つか3つ半と言うか4つくらいの岩崖を越えて尾根道がおだやかになった、と思ったんですが、また容赦のない急登が始まって1183mの標高点の手前からようやく勾配は落ち着きました。立橋尾根は尾根歩きの範疇ではないような気がします。強いて言えば尾根登りです。序盤で身もココロもかなり衰弱してしまいました。
 おはようございます。秩父鉄道武州日野駅です。御花畑駅で天ぷらそばを食べました。元気いっぱいです。ザックから軍手やら杖を引っ張り出して準備完了。
おはようございます。秩父鉄道武州日野駅です。御花畑駅で天ぷらそばを食べました。元気いっぱいです。ザックから軍手やら杖を引っ張り出して準備完了。 駅を出て線路沿いに御花畑駅方向に戻り、踏切を渡ろうとすると「アブナイ!」という大音量の自動音声にびっくりしました。
駅を出て線路沿いに御花畑駅方向に戻り、踏切を渡ろうとすると「アブナイ!」という大音量の自動音声にびっくりしました。 浅間神社(せんげんじんじゃ)の鳥居を過ぎ、
浅間神社(せんげんじんじゃ)の鳥居を過ぎ、 「明ヶ指たまご水(みょうがさすたまごみず)」方向に進みます。
「明ヶ指たまご水(みょうがさすたまごみず)」方向に進みます。 花の供えられた馬頭観音。
花の供えられた馬頭観音。 右手に「そば処 和味(なごみ)」という店が見えてきて、
右手に「そば処 和味(なごみ)」という店が見えてきて、 その向かいの「安谷川木橋 たまご水 へ」の道標をちらりと見て通過すると、
その向かいの「安谷川木橋 たまご水 へ」の道標をちらりと見て通過すると、 和味のすぐ先の駐車場に「周辺散歩マップ」が立っています。ここで道路を離れ、ショートカットのためにマップの向こうに進みます。地形図によるとなだらかな尾根の先でくねくね曲がってきた道路と合流するはずです。
和味のすぐ先の駐車場に「周辺散歩マップ」が立っています。ここで道路を離れ、ショートカットのためにマップの向こうに進みます。地形図によるとなだらかな尾根の先でくねくね曲がってきた道路と合流するはずです。 草ボーボーの踏み跡をたどります。
草ボーボーの踏み跡をたどります。 植林帯に突入します。
植林帯に突入します。 フツーの山道になって
フツーの山道になって 道路(秩父併用林道という林道でした)と合流。
道路(秩父併用林道という林道でした)と合流。 林道の向こうの尾根に踏み跡が続いています。ちょっと迷いましたが取付きます。
林道の向こうの尾根に踏み跡が続いています。ちょっと迷いましたが取付きます。 ダーッと登ってきて
ダーッと登ってきて 尾根を越えるとすぐに林道と合流しました。
尾根を越えるとすぐに林道と合流しました。 「森林管理道 秩父中央線」の分岐を通過します。木製の渋い標識が枝葉に隠れるように立っていました。
「森林管理道 秩父中央線」の分岐を通過します。木製の渋い標識が枝葉に隠れるように立っていました。 旅客機が飛んでいるような音がする水道施設を通過します。
旅客機が飛んでいるような音がする水道施設を通過します。 ココロの警笛を鳴らせば下山時の道間違いはなかったはず、などと思ったのは帰宅していまこの写真を見てのこと。
ココロの警笛を鳴らせば下山時の道間違いはなかったはず、などと思ったのは帰宅していまこの写真を見てのこと。 「治山工事をしています」のチェーンを跨ごうとしたんですが、
「治山工事をしています」のチェーンを跨ごうとしたんですが、 「くくり罠」の警告にちょっとビビります。ちょうどこのあたりが499mの標高点です。
「くくり罠」の警告にちょっとビビります。ちょうどこのあたりが499mの標高点です。 涸れ沢に建っていた祠を見上げ、
涸れ沢に建っていた祠を見上げ、 トンネルをくぐり、
トンネルをくぐり、 立橋尾根の方向が開けていたんですが、見えているのかはっきりしません。
立橋尾根の方向が開けていたんですが、見えているのかはっきりしません。 ゴリゴリに削られた岩壁沿いに歩いてきて
ゴリゴリに削られた岩壁沿いに歩いてきて ここも立橋尾根の方向が開けていたんですが、やはり見えているのかはっきりしません。
ここも立橋尾根の方向が開けていたんですが、やはり見えているのかはっきりしません。 旅客機の音がする水道施設のすぐ先が
旅客機の音がする水道施設のすぐ先が 秩父林道の始点でした。
秩父林道の始点でした。 てくてくと歩きます。秩父林道は勾配をほとんど感じません。登るどころかゆるやかに下ったりもします。
てくてくと歩きます。秩父林道は勾配をほとんど感じません。登るどころかゆるやかに下ったりもします。 おそらくあのとんがったピークが旧立橋山、立橋尾根のてっぺんです。右下は「秩父営林署 日野休憩所」と墨書された看板のある建物です。現役なのでしょうか。573mの標高点はこの建物の向かいあたり。
おそらくあのとんがったピークが旧立橋山、立橋尾根のてっぺんです。右下は「秩父営林署 日野休憩所」と墨書された看板のある建物です。現役なのでしょうか。573mの標高点はこの建物の向かいあたり。 道すがら。安谷川の流れ。
道すがら。安谷川の流れ。 地形図にない林道を右に分け、
地形図にない林道を右に分け、 立橋尾根の取付点、秩父橋に到着です。
立橋尾根の取付点、秩父橋に到着です。 秩父橋から安谷川の流れ。水はゴンゴン流れています。
秩父橋から安谷川の流れ。水はゴンゴン流れています。 ちょっと先の谷(多分、烏帽子谷)の堰堤。こちらもザンザンと水が落ちていました。
ちょっと先の谷(多分、烏帽子谷)の堰堤。こちらもザンザンと水が落ちていました。 安谷川と烏帽子谷に挟まれた立橋尾根に取付きます。「水源かん養保安林 設置 平成十八年度 関東森林管理局長」の標柱から先に踏み跡がのびています。
安谷川と烏帽子谷に挟まれた立橋尾根に取付きます。「水源かん養保安林 設置 平成十八年度 関東森林管理局長」の標柱から先に踏み跡がのびています。 建物があったような草ボーボーの平坦な土地を抜けると
建物があったような草ボーボーの平坦な土地を抜けると いきなりの急登で、見上げると大岩が鎮座しています。
いきなりの急登で、見上げると大岩が鎮座しています。 下調べに従って左に巻きます。
下調べに従って左に巻きます。 踏み跡は小尾根に向かってトラバース(山腹水平移動)していきますが、
踏み跡は小尾根に向かってトラバース(山腹水平移動)していきますが、 「そんなにキツくないんじゃないの?」と踏み跡を離脱して尾根上に向かって這い上がりました。
「そんなにキツくないんじゃないの?」と踏み跡を離脱して尾根上に向かって這い上がりました。 登ってきて
登ってきて 登るんですが、この後がほふく前進で岩場を抜けるような場所もあるとんでもない崖登りでした。写真を撮る余裕はなく、
登るんですが、この後がほふく前進で岩場を抜けるような場所もあるとんでもない崖登りでした。写真を撮る余裕はなく、 なんとかかんとか登ってきました。巻きが足らなかったんでしょうか。先ほどのトラバースを続けていればラクだったんでしょうか。初っ端でかなり疲れてしまいました。
なんとかかんとか登ってきました。巻きが足らなかったんでしょうか。先ほどのトラバースを続けていればラクだったんでしょうか。初っ端でかなり疲れてしまいました。 すぐに現れた大岩の左を這い上がり、
すぐに現れた大岩の左を這い上がり、 キビシい急登から
キビシい急登から キビシい急登です。
キビシい急登です。 やっぱりキビシい急登から
やっぱりキビシい急登から 露岩の尾根になり、ひととき急登を忘れることができました。
露岩の尾根になり、ひととき急登を忘れることができました。 忘れても急登は急登で、
忘れても急登は急登で、 790mあたりでようやくおだやかな尾根道になったかと思うと
790mあたりでようやくおだやかな尾根道になったかと思うと あの先にキツい勾配が見えています。
あの先にキツい勾配が見えています。 ツタに同化しようとしているワイヤーなのか、ワイヤーになりきろうとしているツタなのか、両者が入り混じっていました。
ツタに同化しようとしているワイヤーなのか、ワイヤーになりきろうとしているツタなのか、両者が入り混じっていました。 苔にくるまれた岩がゴロゴロしている場所を抜けると
苔にくるまれた岩がゴロゴロしている場所を抜けると 右から登ってきた小尾根と合流したんですが、
右から登ってきた小尾根と合流したんですが、 尾根はいきなり荒々しくなりました。
尾根はいきなり荒々しくなりました。 登ります。デンジャラス感はありません。ちょっと楽しいです。
登ります。デンジャラス感はありません。ちょっと楽しいです。 登ってきて
登ってきて 安谷川側に下っているワイヤーを眺めたりしたまではよかったんですが、
安谷川側に下っているワイヤーを眺めたりしたまではよかったんですが、 ルートがさっぱりわからない藪に覆われた岩崖に取付きます。
ルートがさっぱりわからない藪に覆われた岩崖に取付きます。 左方向に斜上してきました。と言ってもなんだかわからない写真です。
左方向に斜上してきました。と言ってもなんだかわからない写真です。 踏み跡なのか、たんに藪が薄いのか、そんな山肌をたどります。左に斜上してきてここで右に方向転換、すぐにまた左へ。
踏み跡なのか、たんに藪が薄いのか、そんな山肌をたどります。左に斜上してきてここで右に方向転換、すぐにまた左へ。 道すがら。なんて言っている余裕はないんですが、苦しまぎれの撮影。
道すがら。なんて言っている余裕はないんですが、苦しまぎれの撮影。 体感勾配はほぼ90度です。このときばかりはいつもは煩わしいアセビやらなんやらかんやらの草木は頬ずりしたいくらいの頼もしさでした。まっ、実際は頬ずりと言うか細いのに頑丈な枝葉で顔じゅうをぶたれたんですが。
体感勾配はほぼ90度です。このときばかりはいつもは煩わしいアセビやらなんやらかんやらの草木は頬ずりしたいくらいの頼もしさでした。まっ、実際は頬ずりと言うか細いのに頑丈な枝葉で顔じゅうをぶたれたんですが。 大きな切株の向こうにさらに巨大な岩崖が見えてきました。切株を越え、右に進むと
大きな切株の向こうにさらに巨大な岩崖が見えてきました。切株を越え、右に進むと 断崖の端っこに出てしまいました。馬蹄形の崖が眼前に広がります。
断崖の端っこに出てしまいました。馬蹄形の崖が眼前に広がります。 落ちたら一巻どころか『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(集英社)の全200巻の終わりです。
落ちたら一巻どころか『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(集英社)の全200巻の終わりです。 見上げると、30cmも登れそうにありません。引き返します。
見上げると、30cmも登れそうにありません。引き返します。 振り向いた景色。
振り向いた景色。 右に方向転換したポイントまで戻り、大岩の根元を左へ回り込みます。
右に方向転換したポイントまで戻り、大岩の根元を左へ回り込みます。 回り込み中。
回り込み中。 這い上がってきて
這い上がってきて 岩のてっぺんに立ちました。950mくらい。右端は熊倉山なのかな?
岩のてっぺんに立ちました。950mくらい。右端は熊倉山なのかな? 落ちたら一巻どころか(以下同文)。
落ちたら一巻どころか(以下同文)。 てっぺんを辞し、こんな荒ぶれたヤセ尾根を登ります。
てっぺんを辞し、こんな荒ぶれたヤセ尾根を登ります。 荒ぶれすぎています。
荒ぶれすぎています。 そんな荒ぶれたヤセ尾根から鞍部に下ったらまた屹立する岩崖です。
そんな荒ぶれたヤセ尾根から鞍部に下ったらまた屹立する岩崖です。 いざ取付いてみるとなんとか登れそうな感じなんですが、
いざ取付いてみるとなんとか登れそうな感じなんですが、 右側。
右側。 左側。落ちるなら左です。右は落ちたら一巻(以下同文)。
左側。落ちるなら左です。右は落ちたら一巻(以下同文)。 よじ登ります。
よじ登ります。 岩峰が見えます。あれはいったいどうするんでしょう。
岩峰が見えます。あれはいったいどうするんでしょう。 左に巻くように這い上がってきて
左に巻くように這い上がってきて 這い上がります。
這い上がります。 尾根に復帰しました。巻道と言うか崖登りでした。
尾根に復帰しました。巻道と言うか崖登りでした。 すぐにまた、とんでもない岩崖が立ちふさがりました。1010m圏です。
すぐにまた、とんでもない岩崖が立ちふさがりました。1010m圏です。 またよじ登ります。これって尾根歩き?
またよじ登ります。これって尾根歩き? よじ登ってきて
よじ登ってきて ヤセ尾根の大木に美しい洞を見つけました。怖いので覗けませんでした。そそくさと
ヤセ尾根の大木に美しい洞を見つけました。怖いので覗けませんでした。そそくさと 登ってきて
登ってきて 登ります。
登ります。 崖登りは終わったのでしょうか。疑心暗鬼のまま、急登に取りかかります。
崖登りは終わったのでしょうか。疑心暗鬼のまま、急登に取りかかります。 すぐに左から登ってきた尾根と合流します。1100mあたりです。合流した尾根には青白いルーズソックスのような樹皮はぎ防止ネットをまとったヒノキが並んでいました。
すぐに左から登ってきた尾根と合流します。1100mあたりです。合流した尾根には青白いルーズソックスのような樹皮はぎ防止ネットをまとったヒノキが並んでいました。 ブナでしょうか。枯れた大木を通過します。ルーズソックス軍団を従えて威厳たっぷりです。
ブナでしょうか。枯れた大木を通過します。ルーズソックス軍団を従えて威厳たっぷりです。 1183mの標高点です。古そうな赤テープが木に巻かれていますが、とくになにがあるわけではありません。これでキビシい尾根歩きと言うか崖登りはおしまい、と勝手に思い込んでしまったのが大間違い。立橋尾根の先にはまだキッツい尾根歩きがあったのでした。
1183mの標高点です。古そうな赤テープが木に巻かれていますが、とくになにがあるわけではありません。これでキビシい尾根歩きと言うか崖登りはおしまい、と勝手に思い込んでしまったのが大間違い。立橋尾根の先にはまだキッツい尾根歩きがあったのでした。