今回は下川二俣中間尾根を登り、大羽根山南東尾根を下りました。どちらもテキトーな名付けです。
下川二俣中間尾根は笹尾根の土俵岳のちょっと西、970m圏をてっぺんにして南に下って下川(しもかわ)という渓流の二俣分岐点に没している尾根です。下川は大垣外(おおがいと)地区あたりで上野原市を流れる鶴川の左岸に注ぎ込んでいます。
大羽根山南東尾根は檜原村の大羽根山から南東に下り、南沢にがっつり落ち込んでいる尾根です。
下川二俣中間尾根は沢歩きからの尾根歩きです。地形図を見る限りそのはずでした。
大羽根山南東尾根は森沢への下降が懸念事項です。地形図を見ると、森沢と林道がほぼくっついて並走しているその森沢側に降下するはずです。等高線は詰んでいます。詰み詰みです。ちょっと不安です。この不安は的中してしまいました。
※「標高」は省略しています。
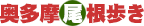
下川二俣中間尾根、大羽根山南東尾根
(1/2)
| ■コース | JR中央本線上野原駅→[START]大垣外バス停→市道→不動の滝→下川→(1時間20分)下川二俣中間尾根取付→下川二俣中間尾根→(1時間30分)笹尾根970m圏→笹尾根→小棡峠→(丸山)→笛吹峠→藤尾分岐→(1時間5分)笹ヶタワノ峰の近く→大羽根山尾根→(15分)大羽根山→大羽根山南東尾根→(1時間15分)林道森沢線→(15分)檜原街道→松坂屋酒店→(50分)[GOAL]檜原温泉センター数馬の湯→温泉センターバス停→JR五日市線武蔵五日市駅 (6時間30分) |
| ■歩いた日 | 2025年9月21日(日) |
※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。
■JR中央本線上野原駅→[START]大垣外バス停→市道→不動の滝→下川→(1時間20分)下川二俣中間尾根取付→下川二俣中間尾根→(1時間30分)笹尾根970m圏
下川二俣中間尾根にアプローチする下川は中流域に不動の滝があることのほか、ほんの少し(後述)の情報しか見つかりませんでした。
おまけに地形図の車道記号(市道)が消えても現場の道はずっと先にのびていて、出発前のイメージトレーニングは水泡と帰してしまいました。
尾根はすんごい急登で始まり、なかなかやむことはなく、雑木のやわらかい曲線を描く木立ややわらかい葉っぱの色がふんわりと背中を押してくれるのでした。
 おはようございます。上野原駅から小菅の湯行きのバスに乗り約30分、大垣外バス停で降りました。バスを追いかける軽トラックに背を向けてすぐ、
おはようございます。上野原駅から小菅の湯行きのバスに乗り約30分、大垣外バス停で降りました。バスを追いかける軽トラックに背を向けてすぐ、 火の見櫓のある道(市道らしい)に入ります。
火の見櫓のある道(市道らしい)に入ります。 大垣外の集落を歩きます。ゆるーいというにはちょっとキツめの坂道がつづきます。
大垣外の集落を歩きます。ゆるーいというにはちょっとキツめの坂道がつづきます。 分岐は「TAKI←」の道標に従って左へ。
分岐は「TAKI←」の道標に従って左へ。 お寺とお墓を抜けると勾配はゆるみ、
お寺とお墓を抜けると勾配はゆるみ、 すぐに「不動の滝入口」です。足場の階段を降ります。
すぐに「不動の滝入口」です。足場の階段を降ります。 7、8分で下川にかかる不動の滝に着きました。2段の滝です。落差は上10m、下2mとネット情報にありました。碑には「大日大聖不動尊」と彫られています。しばらくぶらぶら見学して引き返します。
7、8分で下川にかかる不動の滝に着きました。2段の滝です。落差は上10m、下2mとネット情報にありました。碑には「大日大聖不動尊」と彫られています。しばらくぶらぶら見学して引き返します。 でっかい剣が山腹に安置されていました。来るときには気づきませんでした。
でっかい剣が山腹に安置されていました。来るときには気づきませんでした。 そのまま右上に視線を移すと市道が見えます。薄ーい踏み跡があるようなないような。
そのまま右上に視線を移すと市道が見えます。薄ーい踏み跡があるようなないような。 這い上がってきました。歩いてきた方向の曲がり角に「不動の滝入口」が見えます。すぐそこです。時短になったけれど体力は消費大、ショーットカットとしてはプラマイゼロ、かな。
這い上がってきました。歩いてきた方向の曲がり角に「不動の滝入口」が見えます。すぐそこです。時短になったけれど体力は消費大、ショーットカットとしてはプラマイゼロ、かな。 下川を渡ります。左岸から入渓できそうですが、「水道施設のため立入禁止」」の看板が立っていました。山梨県が砂防工事のために作成した『令和3年度 公共事業事前評価調書(簡易型)』という書類に「本渓流(下川のこと:『奥多摩尾根歩き』注)は流域面積1.53km2の土石流危険渓流である。流域内は崩壊や渓岸浸食が進行し、渓床には不安定土砂、転石が堆積しているとともに、渓岸沿いには立木が密集している。今後の台風や集中豪雨時には、土砂流出、流木による土石流発生の危険が高まっている。」と記されています。恐ろしげな沢です。
下川を渡ります。左岸から入渓できそうですが、「水道施設のため立入禁止」」の看板が立っていました。山梨県が砂防工事のために作成した『令和3年度 公共事業事前評価調書(簡易型)』という書類に「本渓流(下川のこと:『奥多摩尾根歩き』注)は流域面積1.53km2の土石流危険渓流である。流域内は崩壊や渓岸浸食が進行し、渓床には不安定土砂、転石が堆積しているとともに、渓岸沿いには立木が密集している。今後の台風や集中豪雨時には、土砂流出、流木による土石流発生の危険が高まっている。」と記されています。恐ろしげな沢です。市道を先に進みます。
 ゲートが倒木で痛めつけられています。ちょうど地形図の道路が消える地点です。けれども
ゲートが倒木で痛めつけられています。ちょうど地形図の道路が消える地点です。けれども 幅は狭くなったものの道はつづいています。
幅は狭くなったものの道はつづいています。 ここで道はおしまい、と思って
ここで道はおしまい、と思って  下川へどう降りるか観察していたんですが、
下川へどう降りるか観察していたんですが、 おしまいと思っていた道は右にがくっと曲がって山腹を抉りながらまだつづいていました。うーむ。どーしましょ。道をたどるか、
おしまいと思っていた道は右にがくっと曲がって山腹を抉りながらまだつづいていました。うーむ。どーしましょ。道をたどるか、 下川沿いを歩くか。上流には越えられるかどうかわからない滝が見えます。うーむ。
下川沿いを歩くか。上流には越えられるかどうかわからない滝が見えます。うーむ。 下川と右上の道の間にあるようなないような踏み跡があります。決めました。この踏み跡をたどります。
下川と右上の道の間にあるようなないような踏み跡があります。決めました。この踏み跡をたどります。 見えていた滝や連続する小さな滝を高巻き中です。
見えていた滝や連続する小さな滝を高巻き中です。 踏み跡をたどっていくと下川に立ちました。沢歩きの開始です。
踏み跡をたどっていくと下川に立ちました。沢歩きの開始です。 荒れ放題ですが踏み跡はある、のかなあ。
荒れ放題ですが踏み跡はある、のかなあ。 対岸に踏み跡らしい踏み跡がつづいています。
対岸に踏み跡らしい踏み跡がつづいています。 石積の堰堤跡で右岸は進めなくなりました。左岸に渡ります。
石積の堰堤跡で右岸は進めなくなりました。左岸に渡ります。 すぐ上に道が来ていました。水際を歩くのはかなりキビシくなってきていたので道にあがることにしました。
すぐ上に道が来ていました。水際を歩くのはかなりキビシくなってきていたので道にあがることにしました。 道を歩き始めて2、3分。今度こそ終点です。めざす下川二俣中間尾根の右俣にぶつかって道は終わっていました。なんと、市道をずーっと歩いてくればあっさりと下川二俣中間尾根の取付までたどり着けたみたい。ちょっと、とほほ。
道を歩き始めて2、3分。今度こそ終点です。めざす下川二俣中間尾根の右俣にぶつかって道は終わっていました。なんと、市道をずーっと歩いてくればあっさりと下川二俣中間尾根の取付までたどり着けたみたい。ちょっと、とほほ。 右俣を渡ります。
右俣を渡ります。 二俣分岐に立って下川二俣中間尾根を見上げます。
二俣分岐に立って下川二俣中間尾根を見上げます。ザックを降ろしてちょっと休憩。ペットボトルに詰めてきたほうじ茶を飲みます。尾根の左右両裾に踏み跡がのびているようです。
 尾根の最下端で下川の下流を眺めたりもしました。
尾根の最下端で下川の下流を眺めたりもしました。 右俣沿いのそこそこしっかりした道です。山腹をのびています。興味津々ですが、
右俣沿いのそこそこしっかりした道です。山腹をのびています。興味津々ですが、 尾根に取付きます。
尾根に取付きます。 とんでもない勾配を這うように登ってきて
とんでもない勾配を這うように登ってきて 這うように登ります。
這うように登ります。 シンドい登りがつづき、
シンドい登りがつづき、 680mあたりでようやく勾配はゆるみました。
680mあたりでようやく勾配はゆるみました。 760m圏で尾根相はがらりと変わり、右手が雑木になりました。
760m圏で尾根相はがらりと変わり、右手が雑木になりました。 急登は復活。
急登は復活。 パキポキバッキンと枝打ちゾーンを登ります。
パキポキバッキンと枝打ちゾーンを登ります。 886mの標高点あたりを通過します。なんにもございません。たしかに、駅遠、住民少、傾斜地、立ち呑み屋をつくるにはキビシい立地条件です。
886mの標高点あたりを通過します。なんにもございません。たしかに、駅遠、住民少、傾斜地、立ち呑み屋をつくるにはキビシい立地条件です。 境界見出標を通過し、
境界見出標を通過し、 植林の中にビシッと踏み跡が通って、ヒトの気配が強くなり笹尾根の稜線が見えてきました。
植林の中にビシッと踏み跡が通って、ヒトの気配が強くなり笹尾根の稜線が見えてきました。 稜線の手前の巻き道(?)を横断して
稜線の手前の巻き道(?)を横断して 笹尾根の970m圏に立ちました。これにて下川二俣中間尾根はおしましです。【下川二俣中間尾根の動画はこちら→YouTube『奥多摩尾根歩きch』へ】
笹尾根の970m圏に立ちました。これにて下川二俣中間尾根はおしましです。【下川二俣中間尾根の動画はこちら→YouTube『奥多摩尾根歩きch』へ】とくにすることはないのですぐに笹尾根を西へ、大羽根山をめざします。