今回は六ッ石山南東尾根を登り、狩倉山南尾根を下りました。どちらも石尾根から小中沢と長尾沢という沢の出合に落ち込んでいる尾根です。名前はテキトーです。
アプローチは小中沢林道から登山道、小中沢水源巡視道をたどり、小中沢に降り、長尾沢出合まで水線を遡ります。というつもりだったんですか、巡視道をずんずん歩いていたら出合に着いてしまいました。
※「標高」は省略しています。
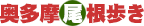
六ッ石山南東尾根、狩倉山南尾根
(1/2)
| ■コース | [START]JR青梅線奥多摩駅→(1時間25分)小中沢林道終点→(40分)小中沢水源巡視道→(40分)六ッ石山南東尾根取付(長尾沢出合)→六ッ石山南東尾根→(2時間5分)六ッ石山→石尾根→(15分)狩倉山→狩倉山南尾根→(1時間10分)長尾沢出合→小中沢水源巡視道→(35分)小中沢林道→(1時間)[GOAL]JR青梅線奥多摩駅 (7時間50分) |
| ■歩いた日 | 2025年11月3日(月) |
※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。
■[START]JR青梅線奥多摩駅→(1時間25分)小中沢林道終点→(40分)小中沢水源巡視道→(40分)六ッ石山南東尾根取付(長尾沢出合)→六ッ石山南東尾根→(2時間5分)六ッ石山
巡視道はめちゃくちゃ歩きやすく、おそらくどこかに小中沢に降りる道があったと思うんですが見逃してしまいました。で、てくてくと歩いていくと小中沢と長尾沢の出合が見えてきました。着いたものはしようがありせん。モノレールが通り、ワサビ田跡が広がる出合に降りました。
六ツ石山南東尾根はほぼ植林に囲まれた尾根です。前半はすんごい急登がつづきます。後半にようやくほんのちょっぴり勾配がゆるみ、巡視道を3度横切って幅広の尾根を喘ぎながら登っていくと石尾根の六ッ石山山頂です。
 おはようございます。奥多摩駅です。ハロウィーンは過ぎたのに登山者の扮装をした人がバス停に並んでいます。 違うか。
おはようございます。奥多摩駅です。ハロウィーンは過ぎたのに登山者の扮装をした人がバス停に並んでいます。 違うか。 駅を出て左へ。丁字路を右折し、奥多摩交番前を過ぎ、氷川大橋を渡ります。右に日原街道を分け、青梅街道を歩き右へ、奥多摩むかし道に進みます。
駅を出て左へ。丁字路を右折し、奥多摩交番前を過ぎ、氷川大橋を渡ります。右に日原街道を分け、青梅街道を歩き右へ、奥多摩むかし道に進みます。 羽黒三田神社(はぐろみたじんじゃ)の表参道です。鳥居の上にもきっつく長い階段がつづきます。
羽黒三田神社(はぐろみたじんじゃ)の表参道です。鳥居の上にもきっつく長い階段がつづきます。 羽黒三田神社に着きました。
羽黒三田神社に着きました。 「神社仏閣道背負う」。神社の裏の山道を登り、
「神社仏閣道背負う」。神社の裏の山道を登り、 階段を上って舗装道路(小中沢林道?)を左へ。
階段を上って舗装道路(小中沢林道?)を左へ。 右に登っていくのは不老林道です。直進します。
右に登っていくのは不老林道です。直進します。 石尾根への登山口を通過します。
石尾根への登山口を通過します。 城(じょう)の集落を通過します。
城(じょう)の集落を通過します。 小中沢林道の終点、三ノ木戸展望所に着きました。
小中沢林道の終点、三ノ木戸展望所に着きました。『奥多摩』(宮内敏雄昭 和刊行会 昭和19 国立国会図書館デジタルコレクション)の353〜354ページに「三ノ木戸の部落は、昭和十三年秋の暴風雨に、日原の山葵田が潰壊に近い大打撃を受けて以來、奥多摩随一の山葵の産出を誇る小仲澤に沿ふ明るい部落だ。此のあたりから下瞰する多摩川の清流の煌き、街道を行く寸人豆馬は南畫そのものである」と書かれています。足元には廃屋が朽ちかけていて背後の山腹にはお屋敷が建っています。木の育ったせいか寸人豆馬は見えませんが、当時は聞こえなかった電車の音が低く届きます。
 展望所の奥にモノレールに沿って登山道がつづいています。んっ、登山道にモノレールが沿っているのかな。
展望所の奥にモノレールに沿って登山道がつづいています。んっ、登山道にモノレールが沿っているのかな。 桟道を渡り、ぐーっと登って
桟道を渡り、ぐーっと登って モノレールをくぐります。
モノレールをくぐります。 道中。
道中。 ロープの先はがっつり崩落しています。右の巻き道へ。
ロープの先はがっつり崩落しています。右の巻き道へ。 怪しげな分岐は右上の「六ッ石山」へ。帰宅後に調べると直進する水平道が水源林巡視道で、出発前に予想していた小中沢の上流域に降りられる道だrったみたい。
怪しげな分岐は右上の「六ッ石山」へ。帰宅後に調べると直進する水平道が水源林巡視道で、出発前に予想していた小中沢の上流域に降りられる道だrったみたい。 次の分岐でトラロープの向こうへ進みます。
次の分岐でトラロープの向こうへ進みます。 快適な道、水源林巡視道(多分)をてくてく歩きます。
快適な道、水源林巡視道(多分)をてくてく歩きます。 山側にしっかりした踏み跡ができている、あまり信用されていない桟道をを渡ります。
山側にしっかりした踏み跡ができている、あまり信用されていない桟道をを渡ります。 「水源巡視道」の道標は右上をさしているけれど小中沢からはなれたくないので直進を選択。
「水源巡視道」の道標は右上をさしているけれど小中沢からはなれたくないので直進を選択。 つくり直されたばかりの桟道を渡ります。
つくり直されたばかりの桟道を渡ります。 道中。このあたりで一天にわかにかき曇りすんごい雨が降ってきました。ザックから防寒着兼雨合羽を、ザックの尻からザックカバーを引っ張り出しで上半身とザックを防水。雨には氷の粒が混じっていて落ち葉の上でぴょんぴょん跳ねていました。
道中。このあたりで一天にわかにかき曇りすんごい雨が降ってきました。ザックから防寒着兼雨合羽を、ザックの尻からザックカバーを引っ張り出しで上半身とザックを防水。雨には氷の粒が混じっていて落ち葉の上でぴょんぴょん跳ねていました。 はるか眼下に小中沢とモノレールがちらりと見えます。降りられそうな道を探しながら先に進みます。
はるか眼下に小中沢とモノレールがちらりと見えます。降りられそうな道を探しながら先に進みます。 崩落地跡を通過します。
崩落地跡を通過します。 激しかった雨はすっかりやみました。乾かすために雨合羽は着たまま、ザックカバーははずして尻尾のようにぶら下げて歩きます。
激しかった雨はすっかりやみました。乾かすために雨合羽は着たまま、ザックカバーははずして尻尾のようにぶら下げて歩きます。 小さな沢を渡って
小さな沢を渡って すぐ、左下に小中沢と長尾沢の出合が見えました。出合にはモノレールが通り、ワサビ田跡が広がっています。
すぐ、左下に小中沢と長尾沢の出合が見えました。出合にはモノレールが通り、ワサビ田跡が広がっています。 右手は下ってくる予定の狩倉山南尾根です。とんでもない勾配です。下れるのでしょうか。そんな不安はとりあえず尾根に置いといて、
右手は下ってくる予定の狩倉山南尾根です。とんでもない勾配です。下れるのでしょうか。そんな不安はとりあえず尾根に置いといて、 巡視道から出合に降りました。六ッ石山南東尾根の最下端です。
巡視道から出合に降りました。六ッ石山南東尾根の最下端です。以下、小中沢について前出の『奥多摩』から引用です。
「小仲澤 六ッ石山西隣の小仲澤ノ峰に發源してと東南に流下、境で多摩川に入る小仲澤は、多摩本流に入る河川では最も山葵の生育に適した澤であるらしく、幅廣のゆったりした河原には足の踏場もない位夥しい綠の波だ。
源流を長尾澤と謂ひ、本谷と會して山葵の裡を本濤し、扇ッ平から東流する金山澤、氷川村の村の字の處で沖ノ指ノ窪を入れ、あとは左岸から三ノ木戸澤・花水澤と併せて多摩川に入る」(182ページ)。
小中沢はワサビの一大生産地だったようです。いまもかな。
 小中沢の下流方向。振り向いて
小中沢の下流方向。振り向いて 六ッ石山南東尾根です。
六ッ石山南東尾根です。 小中沢の上流にモノレールはのび、ずーっとワサビ田跡がつづいているようです。
小中沢の上流にモノレールはのび、ずーっとワサビ田跡がつづいているようです。 六ッ石山南東尾根に取付き、登ってきました。浴槽や瞬間湯沸かし器ややかんやなんやかんやが散乱しています。
六ッ石山南東尾根に取付き、登ってきました。浴槽や瞬間湯沸かし器ややかんやなんやかんやが散乱しています。 どうやら「わさび道場」という小屋がここに建っていたらしい。長尾沢に架かる木橋が見えます。
どうやら「わさび道場」という小屋がここに建っていたらしい。長尾沢に架かる木橋が見えます。 小屋跡から六ッ石山南東尾根の尾根歩き再開です。「60|58」の林班界標が立っています。
小屋跡から六ッ石山南東尾根の尾根歩き再開です。「60|58」の林班界標が立っています。 すんごい勾配を登ってきて
すんごい勾配を登ってきて とんでもない急登がつづきます。ずーっとつづきます。
とんでもない急登がつづきます。ずーっとつづきます。 ずーっとつづいて
ずーっとつづいて 1150m圏で勾配はほんのちょっぴりゆるみました。
1150m圏で勾配はほんのちょっぴりゆるみました。 ほんのちょっぴりです。
ほんのちょっぴりです。 1210m圏で巡視道を横切ります。「60|58」の林班界標が立っています。
1210m圏で巡視道を横切ります。「60|58」の林班界標が立っています。 道中。見上げると黄葉が輝き、
道中。見上げると黄葉が輝き、 眼前のアセビの塊に突入します。
眼前のアセビの塊に突入します。 塊の途中で巡視道を横断しました。1280m圏です。
塊の途中で巡視道を横断しました。1280m圏です。 アセビの濃い〜茂みを抜けてくると
アセビの濃い〜茂みを抜けてくると すっきりとした尾根になりました。
すっきりとした尾根になりました。 すっきりと、から、さっぱりとした尾根になりました。なんかそんな感じ。
すっきりと、から、さっぱりとした尾根になりました。なんかそんな感じ。 1380m圏でまたまた巡視道を横断します。林班界標はおなじみの「60|58」。
1380m圏でまたまた巡視道を横断します。林班界標はおなじみの「60|58」。 幅広急登の頭上に青い空が広がっています。
幅広急登の頭上に青い空が広がっています。 登ってきて
登ってきて 六ッ石山の山頂に到着しました。これにて六ッ石山南東尾根はおしまいです。風が強いです。山頂には三等三角点が設置(赤帽白ポールの右)されています。標高は1478.86m、基準点名は境。境は東の日原川沿いにある地名でしょうか。ちなみに前出の『奥多摩』によるとここを六ッ石山とするのは誤りで、小中沢ノ峰あるいはタル沢ノ峰と呼ぶのが正しいらしい。タル沢は日原側の沢です。本来の六ッ石山はこれから向かう狩倉山への道中にある六ッ石神社が建っている場所だとしています。
六ッ石山の山頂に到着しました。これにて六ッ石山南東尾根はおしまいです。風が強いです。山頂には三等三角点が設置(赤帽白ポールの右)されています。標高は1478.86m、基準点名は境。境は東の日原川沿いにある地名でしょうか。ちなみに前出の『奥多摩』によるとここを六ッ石山とするのは誤りで、小中沢ノ峰あるいはタル沢ノ峰と呼ぶのが正しいらしい。タル沢は日原側の沢です。本来の六ッ石山はこれから向かう狩倉山への道中にある六ッ石神社が建っている場所だとしています。強風のなか、ちょっと休憩します。
六ッ石山南東尾根を登った映像です(三ノ木戸展望所→登山道→水源巡視道→小中沢と長尾沢の出合→六ッ石山南東尾根→六ッ石山)。