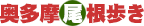
小焼山北尾根、(三頭沢遊歩道)
(2/2)
■小焼山→三頭尾根→神楽入ノ峰→(1時間30分)三頭山(西峰)→(15分)ムシカリ峠→ブナの路→(45分)三頭大滝→ケヤキの路→奥多摩周遊道路→三頭沢遊歩道→(40分)奥多摩周遊道路旧料金所→(25分)[GOAL]檜原温泉センター数馬の湯→温泉センターバス停→JR五日市線武蔵五日市駅
小焼山から三頭山(西峰)までは、三頭尾根の上部です。神楽入ノ峰と1510m圏のピークの登りがシンドかつたです。雲に覆われた尾根歩きも悪くはないんですが気温も湿度も高く、たんたんたんと我慢我慢の尾根歩きでした。
三頭山からはムシカリ峠、ブナの路を経て三頭大滝を見物し、奥多摩周遊道路をちょっと歩いて三頭沢遊歩道へ離脱、数馬の湯まで歩きました。遊歩道は何度も歩いているんですが、なぜか飽きません。廃トイレや少々デンジャラスな橋が尾根歩きの締めに華を添えるから、かな?
 80年も立ちつづけるわけにはいけません。小焼山の山頂を辞し、三頭尾根を三頭山に向かいます。
80年も立ちつづけるわけにはいけません。小焼山の山頂を辞し、三頭尾根を三頭山に向かいます。 急降下から始まり、
急降下から始まり、 少々バテ気味なので巻けるピークは巻きます。
少々バテ気味なので巻けるピークは巻きます。 ここは重要な分岐です。左に歩くと三頭尾根の北面を巻き、三頭山から北西に下る都県境のヌカザス尾根に向かいます。めざす三頭山は尾根上へ。
ここは重要な分岐です。左に歩くと三頭尾根の北面を巻き、三頭山から北西に下る都県境のヌカザス尾根に向かいます。めざす三頭山は尾根上へ。 小さな登り下りはいくつかあったんですが、これは大物です。
小さな登り下りはいくつかあったんですが、これは大物です。 だらだらとした登りがようやく終わったと思ったら今度は急登です。
だらだらとした登りがようやく終わったと思ったら今度は急登です。 岩ゴツゾーンを登って
岩ゴツゾーンを登って ひーこらぜーぜーと登って登って登り詰めると
ひーこらぜーぜーと登って登って登り詰めると 神楽入ノ峰の山頂でした。このあたりに1447mの標高点が設定されています。先に進みます。
神楽入ノ峰の山頂でした。このあたりに1447mの標高点が設定されています。先に進みます。 景色がよさそうな岩場ですが見えるのは薄灰色の雲と薄墨のような山影ばかりです。
景色がよさそうな岩場ですが見えるのは薄灰色の雲と薄墨のような山影ばかりです。 キッツい勾配をはーひーぜーぜーと登ってきて1510m圏のピークです。
キッツい勾配をはーひーぜーぜーと登ってきて1510m圏のピークです。 南西に下っているのはかつて登った長作尾根です。
南西に下っているのはかつて登った長作尾根です。 ピークから下ってきてからの急登です。山頂直下の急登です。
ピークから下ってきてからの急登です。山頂直下の急登です。 ではありませんでした。急登が終わってもゆるーく登っていきます。
ではありませんでした。急登が終わってもゆるーく登っていきます。 ようやく三頭山(西峰)の山頂に到着。
ようやく三頭山(西峰)の山頂に到着。 立派な山頂標識が立っていますが三等三角点が設置されているのは西峰ではなく東峰です。
立派な山頂標識が立っていますが三等三角点が設置されているのは西峰ではなく東峰です。 うーむ、
うーむ、 です。
です。 とっとと山頂を辞します。階段がつづき
とっとと山頂を辞します。階段がつづき ムシカリ峠です。左折して「ブナの路」を下って三頭大滝をめざします。道標に「三頭大滝 30分」と書かれていますがかなりそーとーなスピードで駆け下りないと30分では無理だと思います。
ムシカリ峠です。左折して「ブナの路」を下って三頭大滝をめざします。道標に「三頭大滝 30分」と書かれていますがかなりそーとーなスピードで駆け下りないと30分では無理だと思います。 けれども頑張ってみました。
けれども頑張ってみました。 どがどがと下ります。敷かれた石はわたくしにはプラマイゼロです。足首をくじきそうでちょっと怖いです。
どがどがと下ります。敷かれた石はわたくしにはプラマイゼロです。足首をくじきそうでちょっと怖いです。 沢を6回渡り、
沢を6回渡り、 橋を渡ると
橋を渡ると すぐに三頭大滝の落ち口です。ちらりと覗き、
すぐに三頭大滝の落ち口です。ちらりと覗き、 滝見橋から落差35mの三頭大滝を見物します。ムシカリ峠からここまで頑張って急ぎましたが45分かかりました。
滝見橋から落差35mの三頭大滝を見物します。ムシカリ峠からここまで頑張って急ぎましたが45分かかりました。 チップの敷かれたゴージャスな道をちょっと下った東屋の横から「ケヤキの路」を下ります。
チップの敷かれたゴージャスな道をちょっと下った東屋の横から「ケヤキの路」を下ります。 いくつもの苔むした石積の堰堤を過ぎます。上流部は水が流れていませんが沢沿いを下るにしたがってだんだん水の流れる音が大きくなってきました。
いくつもの苔むした石積の堰堤を過ぎます。上流部は水が流れていませんが沢沿いを下るにしたがってだんだん水の流れる音が大きくなってきました。 ずんずん下っていきます。
ずんずん下っていきます。 奥多摩周遊道路が見えてきました。
奥多摩周遊道路が見えてきました。 周遊道路を200mほど下るとガードケーブルの向こうに「都民の森・三頭山」「平地区・数馬バス停」と書かれた道標が立っています。ガードケーブルをよいしょと乗り越えて「平地区・数馬バス停」方面へ下ります。
周遊道路を200mほど下るとガードケーブルの向こうに「都民の森・三頭山」「平地区・数馬バス停」と書かれた道標が立っています。ガードケーブルをよいしょと乗り越えて「平地区・数馬バス停」方面へ下ります。 最初は小尾根の急降下です。
最初は小尾根の急降下です。 三頭沢沿いに出ると道は平坦になり、道標が沢を挟む場所で渡渉。
三頭沢沿いに出ると道は平坦になり、道標が沢を挟む場所で渡渉。 大きな堰堤を過ぎ、
大きな堰堤を過ぎ、 穴の開いた木橋をおそるおそる渡り、
穴の開いた木橋をおそるおそる渡り、 大岩が並べられた広場や廃トイレを過ぎ、
大岩が並べられた広場や廃トイレを過ぎ、 足場板の橋をまたおそるおそる渡ります。左の木橋は朽ち果てつつあります。
足場板の橋をまたおそるおそる渡ります。左の木橋は朽ち果てつつあります。 かつてはかなり人気のコースだったんだろうな、となんとなく思う遊歩道です。廃ホテルが立ち並ぶバブル期に栄えたリゾート地の雰囲気に似ています。
かつてはかなり人気のコースだったんだろうな、となんとなく思う遊歩道です。廃ホテルが立ち並ぶバブル期に栄えたリゾート地の雰囲気に似ています。 菅平の滝をちらりと見下ろし、
菅平の滝をちらりと見下ろし、 奥多摩周遊道路の旧料金所まで下ってきました。道路を横断し、三頭沢沿いの旅館通りへ。
奥多摩周遊道路の旧料金所まで下ってきました。道路を横断し、三頭沢沿いの旅館通りへ。 足の神様に立ち寄ります。
足の神様に立ち寄ります。 檜原街道に合流し、九頭龍神社(左上)を過ぎ、数馬バス停を過ぎ、666mの標高点のすぐそばの松坂酒店(右上)で缶ビールを購入。行儀よく歩き飲みしながら檜原温泉センター(下)へ。ひと風呂浴びたあと、瓶ビールと舞茸の天ぷらの脳内映像に我を忘れそうになりながら食堂に向かったんですが、バスの時刻のタイミングがよろしくありません。いま食堂に入ると2時間以上も居座ることになります。居酒屋じゃないんでちょっと気が引けます。もう1回、風呂に入るか、などと悩んだんですがもうすぐ出発するバスに乗ることにしました。後ろ髪を激しく引っ張られながら温泉センター前のバス停に向かいました。
檜原街道に合流し、九頭龍神社(左上)を過ぎ、数馬バス停を過ぎ、666mの標高点のすぐそばの松坂酒店(右上)で缶ビールを購入。行儀よく歩き飲みしながら檜原温泉センター(下)へ。ひと風呂浴びたあと、瓶ビールと舞茸の天ぷらの脳内映像に我を忘れそうになりながら食堂に向かったんですが、バスの時刻のタイミングがよろしくありません。いま食堂に入ると2時間以上も居座ることになります。居酒屋じゃないんでちょっと気が引けます。もう1回、風呂に入るか、などと悩んだんですがもうすぐ出発するバスに乗ることにしました。後ろ髪を激しく引っ張られながら温泉センター前のバス停に向かいました。山の神様、地権者の皆様、きょうもありがとうございました。小焼山北尾根にすんなり取付けたのは僥倖でしたが初っ端の濃厚な藪にはヤラれました。禍福は糾える縄の如し、人間万事塞翁が馬でございます。また、よろしくお願いします。