今回は井戸小屋尾根(いどこやおね)を登り、沖ノ指山南尾根(おきのさすやまみなみおね)を下りました。
井戸小屋尾根は水根(みずね)、六ツ石山(むついしやま)間のトオノクボあたりをてっぺんにしてほぼ南に延び、中山集落の西側を通って小河内ダム近くの多摩川に没している尾根です。滝ノリ沢と中山沢という沢に挟まれています。尾根の名前は『奥多摩』(宮内敏雄 著 百水社 刊)の11ページの地図によります。できるだけ下から登ろうと「奥多摩むかし道」から歩き始めました。
沖ノ指山南尾根はトオノクボから東に延びている榛ノ木尾根(はんのきおね)にある沖ノ指山(おきのさすやま)というピークをてっぺんにしてほぼ南に延びている尾根です。分岐しているので下端はここといって特定できません。わたくしは南にポコリと飛び出た道所(どうどころ)という集落を目指して下りました。
※オプショナルツアーの仏岩見学はMマップを参考にさせていただきました。
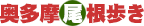
井戸小屋尾根、沖ノ指山南尾根
(1/2)
| ■コース | JR青梅線奥多摩駅→[START]桃ケ沢バス停→奥多摩むかし道→井戸小屋尾根→(40分)浅間神社→仏岩(往復)→(2時間30分)榛ノ木尾根→(30分)沖ノ指山→沖ノ指山南尾根→(1時間50分)道所→奥多摩むかし道→青梅街道→(1時間20分)[GOAL]JR青梅線奥多摩駅 |
| ■歩いた日 | 2020年3月13日(金) |
※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。
■JR青梅線奥多摩駅→[START]桃ケ沢バス停→奥多摩むかし道→井戸小屋尾根→(40分)浅間神社→仏岩(往復)→(2時間30分)榛ノ木尾根→(30分)沖ノ指山
井戸小屋尾根はヤセたりまーるく広がったり岩ゴツだったりザレていたり急勾配だったり緩やかになったり、いろいろな表情がありました。オプションの仏岩の見学も面白かったです。
 おはようございます。奥多摩駅前から小菅の湯行きバスに乗って15分足らず、桃ケ沢バス停で降りました。平日ですが、立ち客も2、3人いました。
おはようございます。奥多摩駅前から小菅の湯行きバスに乗って15分足らず、桃ケ沢バス停で降りました。平日ですが、立ち客も2、3人いました。バス停から青梅街道を離れ、左に下り、奥多摩むかし道(以下、むかし道)との合流点に向かいます。
 中山橋(なかやまはし)という橋を渡り、その先のトンネルをくぐります。
中山橋(なかやまはし)という橋を渡り、その先のトンネルをくぐります。
 左下にむかし道が見えてきました。
左下にむかし道が見えてきました。
 あそこです。
あそこです。
 ここです。ここからむかし道を歩き、井戸小屋尾根を目指します。ザックから新品の軍手(愛用していた軍手は前回の流血事故でゴミになりました)や杖、うす水色のタオル(愛用していた深紅のタオルは前回の流血事故で雑巾に昇華しました)を引っ張りだして正装に。出発します。
ここです。ここからむかし道を歩き、井戸小屋尾根を目指します。ザックから新品の軍手(愛用していた軍手は前回の流血事故でゴミになりました)や杖、うす水色のタオル(愛用していた深紅のタオルは前回の流血事故で雑巾に昇華しました)を引っ張りだして正装に。出発します。
 地図上ではあの奥が井戸小屋尾根です。
地図上ではあの奥が井戸小屋尾根です。
 これは井戸小屋尾根の下端方向。何だかよくわかりません。多摩川の音が聞こえてくるばかりです。
これは井戸小屋尾根の下端方向。何だかよくわかりません。多摩川の音が聞こえてくるばかりです。
 これは見上げたところ。ここから取り付いてもいいんですが、どーせすぐにむかし道に合流してしまいす。むかし道を進みます。
これは見上げたところ。ここから取り付いてもいいんですが、どーせすぐにむかし道に合流してしまいす。むかし道を進みます。
 むかし道に沿って建物跡があります。
むかし道に沿って建物跡があります。
 振り返ると小河内(おごうち)ダムが見えます。
振り返ると小河内(おごうち)ダムが見えます。
 建物跡の奥に行ってみました。民家跡のようには思えません。ヒミツの施設だったに違いない、などと勝手なことを思いながらむかし道に戻ります。
建物跡の奥に行ってみました。民家跡のようには思えません。ヒミツの施設だったに違いない、などと勝手なことを思いながらむかし道に戻ります。
 こんな道を歩いていきます。
こんな道を歩いていきます。
 この写真だとよくわかりませんが、奥に見える飾り付けしていないデコレーションケーキみたいな謎の大きな施設を通過します。
この写真だとよくわかりませんが、奥に見える飾り付けしていないデコレーションケーキみたいな謎の大きな施設を通過します。
 鉄塔を通過します。
鉄塔を通過します。
 七分咲きのサクラを通過します。
七分咲きのサクラを通過します。
 逆くの字に曲がります。
逆くの字に曲がります。
 古そうな林班界標を通過すると、
古そうな林班界標を通過すると、
 すぐに浅間神社(せんげんじんじゃ)への入り口です。
すぐに浅間神社(せんげんじんじゃ)への入り口です。
 小河内ダムと奥多摩湖がよく見えます。
小河内ダムと奥多摩湖がよく見えます。
 浅間神社。桃ケ沢バス停から約40分かかりました。ここから井戸小屋尾根歩きが本格的に始まります。神社の裏に回り込みます。
浅間神社。桃ケ沢バス停から約40分かかりました。ここから井戸小屋尾根歩きが本格的に始まります。神社の裏に回り込みます。
 すぐに髭の木配水所です。尾根の上にデンと建っています。髭の木って何なんでしょう。右に回り込みました。
すぐに髭の木配水所です。尾根の上にデンと建っています。髭の木って何なんでしょう。右に回り込みました。
 回り込み中。中山の集落と多摩川に落ち込む何本もの尾根。
回り込み中。中山の集落と多摩川に落ち込む何本もの尾根。
 配水所の裏はこんな感じで、ちょっとした崩落地でした。獣たちもさんざん掘り起こしているようです。
配水所の裏はこんな感じで、ちょっとした崩落地でした。獣たちもさんざん掘り起こしているようです。
 杭が崩れ落ちるのも時間の問題でしょう。
杭が崩れ落ちるのも時間の問題でしょう。
 尾根らしい尾根になりました。
尾根らしい尾根になりました。
 グーッと登っていきます。
グーッと登っていきます。
 「用水地道」と刻印されたコンクリート杭。「四」です。「七」までは確認したんですが、後はあるのかないのか不明です。
「用水地道」と刻印されたコンクリート杭。「四」です。「七」までは確認したんですが、後はあるのかないのか不明です。
 急登です。
急登です。
 登ってきました。
登ってきました。
 岩ゴツです。
岩ゴツです。
 登ってきて、
登ってきて、
 登ると、
登ると、
 左や
左や
 右から尾根がにじり寄ってきました。
右から尾根がにじり寄ってきました。
 尾根の合流点。770m圏です。「用水地道」の番号は「七」。だからどーした、と言われても困ります。
尾根の合流点。770m圏です。「用水地道」の番号は「七」。だからどーした、と言われても困ります。
 鞍部をしっかりした道が横切っています。819mの標高点直下です。
鞍部をしっかりした道が横切っています。819mの標高点直下です。
 ここから仏岩のオプショナルツアーに出かけます。左の道へ。
ここから仏岩のオプショナルツアーに出かけます。左の道へ。切り替え画像は「Mマップ No.10改」です。
 こんな道を歩き、
こんな道を歩き、
 あれか? と思ったんですが、これは違います。もう少し先の
あれか? と思ったんですが、これは違います。もう少し先の
 こちらが仏岩です。手前と奥にも巨大な岩が突き出ています。
こちらが仏岩です。手前と奥にも巨大な岩が突き出ています。
 手前の岩。岩のてっぺんには大きなブナが立っています。
手前の岩。岩のてっぺんには大きなブナが立っています。
 奥の岩。こちらも岩のてっぺんにブナが立っていました。
奥の岩。こちらも岩のてっぺんにブナが立っていました。
 動き出しそうです。
動き出しそうです。
 吠えています。
吠えています。
 眼下の滝ノリ沢。2019年10月の台風19号の影響でしょうか、沢床は岩で埋め尽くされています。
眼下の滝ノリ沢。2019年10月の台風19号の影響でしょうか、沢床は岩で埋め尽くされています。
 引き返します。楽しかったです! さようなら! 奇岩の奇観!
引き返します。楽しかったです! さようなら! 奇岩の奇観!
 どのあたりが仏だったんだろう、などと考えながら歩いていると井戸小屋尾根に戻りました。仏岩との往復で20数分でした。
どのあたりが仏だったんだろう、などと考えながら歩いていると井戸小屋尾根に戻りました。仏岩との往復で20数分でした。
 左に巻き道らしきものが伸びているんですが、岩ゴツのヤセ尾根に取り付きます。
左に巻き道らしきものが伸びているんですが、岩ゴツのヤセ尾根に取り付きます。
 危険というわけではありませんが、
危険というわけではありませんが、
 とくに右側は冗談でも落ちてはいけません。「ハッハハ、落ちちゃったんだよ」ではすみません。
とくに右側は冗談でも落ちてはいけません。「ハッハハ、落ちちゃったんだよ」ではすみません。
 819mの標高点を通過します。とくになにもありません。
819mの標高点を通過します。とくになにもありません。
 このあたりちょっと地形が複雑ですが、まっすぐ進みます。
このあたりちょっと地形が複雑ですが、まっすぐ進みます。
 尾根をゆるーく縫うように道がありましたが、メンドーなのでテキトーに尾根上と思われるところを登っていきます。
尾根をゆるーく縫うように道がありましたが、メンドーなのでテキトーに尾根上と思われるところを登っていきます。
 熊岩を通過します。850mあたり。
熊岩を通過します。850mあたり。
 赤矢印を通過します。
赤矢印を通過します。
 樹間の向こうに見えるあの尾根の向こうの見えていない尾根がこれから下る沖ノ指山南尾根です。不要な情報でした。
樹間の向こうに見えるあの尾根の向こうの見えていない尾根がこれから下る沖ノ指山南尾根です。不要な情報でした。
 まーるく広がった尾根をテキトーに登っていきます。920m圏です。
まーるく広がった尾根をテキトーに登っていきます。920m圏です。
 登ってきました。ダラーンとした感じです。
登ってきました。ダラーンとした感じです。
 ちょっと尾根幅が絞られてきました。
ちょっと尾根幅が絞られてきました。
 そこそこ急登でした。
そこそこ急登でした。
 1050mあたりで作業道を横断します。
1050mあたりで作業道を横断します。
 ザレザレの急登でなんとも登りづらいです。
ザレザレの急登でなんとも登りづらいです。
 登ってきました。
登ってきました。
 登ります。
登ります。
 振り返れば奥多摩湖。ほうじ茶を一口飲んでちょっと休憩。
振り返れば奥多摩湖。ほうじ茶を一口飲んでちょっと休憩。
 崩落(雨裂?)の上端を眺めながら通過します。
崩落(雨裂?)の上端を眺めながら通過します。
 1150mあたりで作業道を横切ります。
1150mあたりで作業道を横切ります。
 西に伸びる作業道。
西に伸びる作業道。
 東に延びる作業道。
東に延びる作業道。
 作業道から尾根を見上げると4本の赤帽白杭が見えました。
作業道から尾根を見上げると4本の赤帽白杭が見えました。
 4本目の杭。5本目の杭が見えています。
4本目の杭。5本目の杭が見えています。
 5本目の杭。6本目の杭がてっぺんに見えています。
5本目の杭。6本目の杭がてっぺんに見えています。
 登ってきて、
登ってきて、
 6本目の杭です。ゴールまでもう少しです。
6本目の杭です。ゴールまでもう少しです。
 榛ノ木尾根に合流。ロープが張られているところに出ました。
榛ノ木尾根に合流。ロープが張られているところに出ました。
 あちらから登ってきました。これにて井戸小屋尾根はおしまいです。
あちらから登ってきました。これにて井戸小屋尾根はおしまいです。
 こちらはトオノクボへ。
こちらはトオノクボへ。
 沖ノ指山は反対側のこちら。ほうじ茶を飲んで休憩します。きょうは暖かいです。ワラビでも生えてないかとブラブラしましたが、皆無。もう一口ほうじ茶を飲んで出発です。
沖ノ指山は反対側のこちら。ほうじ茶を飲んで休憩します。きょうは暖かいです。ワラビでも生えてないかとブラブラしましたが、皆無。もう一口ほうじ茶を飲んで出発です。
 シンメトリーなモミ(多分)を通過します。
シンメトリーなモミ(多分)を通過します。
 先ほど単独の山ガールとすれ違いました。だからどーした、と言われても困ります。
先ほど単独の山ガールとすれ違いました。だからどーした、と言われても困ります。
 巨大な電波反射板を通過します。直線的に伐採された空間の先に小河内ダムと奥多摩湖が見えました。
巨大な電波反射板を通過します。直線的に伐採された空間の先に小河内ダムと奥多摩湖が見えました。
 テクテクと尾根を下っていたんですが、ここまで来て「何かヘン」と思いました。スマホGPSで確認するとやはり違う尾根です。なぜ「何かヘン」と思ったのかは謎。不思議です。
テクテクと尾根を下っていたんですが、ここまで来て「何かヘン」と思いました。スマホGPSで確認するとやはり違う尾根です。なぜ「何かヘン」と思ったのかは謎。不思議です。
 榛ノ木尾根はあちらです。どこから登ってきたのかなあ、どこに行くのかなあ、などと山ガールのことを考えながら歩いていたわけでは決してないんですが、間違っちゃいました。トラバースして尾根を移ります。
榛ノ木尾根はあちらです。どこから登ってきたのかなあ、どこに行くのかなあ、などと山ガールのことを考えながら歩いていたわけでは決してないんですが、間違っちゃいました。トラバースして尾根を移ります。
 榛ノ木尾根に復帰。
榛ノ木尾根に復帰。
 植林帯に入ってすぐ、
植林帯に入ってすぐ、
 登山道の右にある岩塊が沖ノ指山です。
登山道の右にある岩塊が沖ノ指山です。
 登ります。
登ります。
 沖ノ指山の山頂に到着。
沖ノ指山の山頂に到着。
 ちょっとお腹が空いたし時間の余裕もあるのでご飯にします。メニューはわたくし製ツナサンドと永谷園「らくらくみそ汁」の「油あげ」。アップ画像は不要ですか。あーそーですか。おいしかったですよっ!
ちょっとお腹が空いたし時間の余裕もあるのでご飯にします。メニューはわたくし製ツナサンドと永谷園「らくらくみそ汁」の「油あげ」。アップ画像は不要ですか。あーそーですか。おいしかったですよっ!
 味噌汁は好きです。かき混ぜるとワカメが浮いてきました。
味噌汁は好きです。かき混ぜるとワカメが浮いてきました。
 山頂の様子。
山頂の様子。
 山頂の様子。
山頂の様子。
 山頂から登山道を見下ろしたところ。
山頂から登山道を見下ろしたところ。
© okutamaonearuki