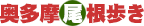
兵ノ沢右岸尾根、二子山東尾根、(旧名栗街道)
(3/3)
■旧名栗街道→(45分)山伏峠→(1時間5分)名郷→新井不動尊(不動の湧水)→伯林寺→(2時間)[GOAL]さわらびの湯→ノーラ名栗・さわらびの湯バス停→西武池袋線飯能駅
山伏峠から先の旧名栗街道は名前のわからない沢にだーっとテキトーに下り、樹木に囲まれたいかにも古道っぽい道に立つと、途切れそうで途切れない道がずーっとつづきました。新井不動尊の不動の湧水、おいしかったです。
 二子山の登山口、林道焼山線を右手に見て
二子山の登山口、林道焼山線を右手に見て カカシも右手に見て
カカシも右手に見て 真っすぐのびたルート66みたいな(行ったことないけれど)県道をひたすら歩きます。ルート66というよりはしまなみ海道のどこかの島にこんな道があったなと、ふと思い出したりしていると
真っすぐのびたルート66みたいな(行ったことないけれど)県道をひたすら歩きます。ルート66というよりはしまなみ海道のどこかの島にこんな道があったなと、ふと思い出したりしていると 横瀬町から飯能市へ。
横瀬町から飯能市へ。 ルート66の右に武川岳(たけがわだけ)への登山道、
ルート66の右に武川岳(たけがわだけ)への登山道、 左に伊豆ヶ岳への登山道を過ぎ、
左に伊豆ヶ岳への登山道を過ぎ、 山伏峠を越えます。法螺貝の音がブゥォーと聞こえてきます。ん、バイクか。
山伏峠を越えます。法螺貝の音がブゥォーと聞こえてきます。ん、バイクか。 山伏峠を越えてすぐ、怪しげな踏み跡が樹林の中に消えています。これが『詳細図』に記載されている紫色の破線だと思われます。
山伏峠を越えてすぐ、怪しげな踏み跡が樹林の中に消えています。これが『詳細図』に記載されている紫色の破線だと思われます。 踏み入ります。そこそこしっかりした道というか踏み跡がつづいています。
踏み入ります。そこそこしっかりした道というか踏み跡がつづいています。 けれども、すぐに小さな涸れ沢あたりで道は消失。眼下の沢沿いに道らしいものがあるようなないような。ズッザズズザとテキトーに下ります。
けれども、すぐに小さな涸れ沢あたりで道は消失。眼下の沢沿いに道らしいものがあるようなないような。ズッザズズザとテキトーに下ります。 もう少し下っていくと
もう少し下っていくと 道らしい道にぶつかりました。歩きます。
道らしい道にぶつかりました。歩きます。 谷で流されていたりしますが道はつづきます。
谷で流されていたりしますが道はつづきます。 『詳細図』に「じじい・ばばあ地蔵尊」と記載されている石仏。
『詳細図』に「じじい・ばばあ地蔵尊」と記載されている石仏。 左は「明智真禅定尼」、
左は「明智真禅定尼」、 右は「明智真禅定門」と彫られています。つまり左が「ばばあ」で右が「じじい」。「じじい」像には天保10(1839)年に上名栗峠の孫左エ門が設置したこと、「ばばあ」像には孫左エ門の妻であることが彫られています。先立たれた妻のために像を建て、ひとりじゃ寂しかろうと「じじい」が自分の分も建てた、んでしょうか。上名栗峠はいまの山伏峠なのでしょうか。
右は「明智真禅定門」と彫られています。つまり左が「ばばあ」で右が「じじい」。「じじい」像には天保10(1839)年に上名栗峠の孫左エ門が設置したこと、「ばばあ」像には孫左エ門の妻であることが彫られています。先立たれた妻のために像を建て、ひとりじゃ寂しかろうと「じじい」が自分の分も建てた、んでしょうか。上名栗峠はいまの山伏峠なのでしょうか。 谷に向かって下っていきます。糸ようじみたいな木橋が見えます。
谷に向かって下っていきます。糸ようじみたいな木橋が見えます。 糸ようじよりは丈夫そうですがとても身をまかせる気にはなれません。ちょっと上流で沢を渡って道の先に進みます。
糸ようじよりは丈夫そうですがとても身をまかせる気にはなれません。ちょっと上流で沢を渡って道の先に進みます。 枝葉に埋もれつつありますが道らしさは残っています。
枝葉に埋もれつつありますが道らしさは残っています。 ガツンと切れ落ちた場所に出ました。眼下には道路が見え、自動車やバイク、自転車が行き交っています。左手は小尾根に向かって薄い踏み跡があるようないような。右手は沢に向かってしっかりした道がのびています。
ガツンと切れ落ちた場所に出ました。眼下には道路が見え、自動車やバイク、自転車が行き交っています。左手は小尾根に向かって薄い踏み跡があるようないような。右手は沢に向かってしっかりした道がのびています。 しっかりをたどります。
しっかりをたどります。 沢の対岸に道らしきものが見えます。
沢の対岸に道らしきものが見えます。 沢にがっくんと降り、対岸に登ります。
沢にがっくんと降り、対岸に登ります。 ちょっと上流に大きな堰堤がそびえていました。
ちょっと上流に大きな堰堤がそびえていました。 右岸を歩きますがすぐに道はあやふやに。沢沿いか登るか。濃い踏み跡は山腹を上がっています。下流に見える堰堤を高巻く踏み跡に違いありません。
右岸を歩きますがすぐに道はあやふやに。沢沿いか登るか。濃い踏み跡は山腹を上がっています。下流に見える堰堤を高巻く踏み跡に違いありません。 ふふふ、ピンポーンです。堰堤を高巻きます。んっ、沢沿いの道が登ってきました。どちらでもよかったみたい。
ふふふ、ピンポーンです。堰堤を高巻きます。んっ、沢沿いの道が登ってきました。どちらでもよかったみたい。 堰堤を越え、下ってきました。「沢口堰堤」という銘板が埋められていました。
堰堤を越え、下ってきました。「沢口堰堤」という銘板が埋められていました。 ヘアピンカーブの頂点に向かって下ります。
ヘアピンカーブの頂点に向かって下ります。 あちらから下ってきて旧名栗街道(県道53号)のつづきを歩きます。
あちらから下ってきて旧名栗街道(県道53号)のつづきを歩きます。 どうやらこの鉄階段はショートカットぽいです。
どうやらこの鉄階段はショートカットぽいです。 ヘアピンカーブをショーットカットできました。お得感いっぱいの階段でした。
ヘアピンカーブをショーットカットできました。お得感いっぱいの階段でした。 馬頭観世音を過ぎます。
馬頭観世音を過ぎます。 名郷の交差点近くにある中屋商店の軒下を借りてちょっと一休み。
名郷の交差点近くにある中屋商店の軒下を借りてちょっと一休み。 南無新井不動尊です。扉から堂の中を覗くと不動明王がえらく怒っていました。
南無新井不動尊です。扉から堂の中を覗くと不動明王がえらく怒っていました。 境内の不動の名水をいただきます。奥に名前のわからない沢の細い滝が勢いよく流れ落ちています。沢の上流からステンレスの流し台まで導水管が引かれています。とてもおいしいです。日曜日ごとに有間ダムと不動の名水に来ているというライダーのお兄さんとちょっと話をして出発します。
境内の不動の名水をいただきます。奥に名前のわからない沢の細い滝が勢いよく流れ落ちています。沢の上流からステンレスの流し台まで導水管が引かれています。とてもおいしいです。日曜日ごとに有間ダムと不動の名水に来ているというライダーのお兄さんとちょっと話をして出発します。 馬頭観音を擁壁がよけています。馬頭観音の建立は昭和2(1927)年。若手です。
馬頭観音を擁壁がよけています。馬頭観音の建立は昭和2(1927)年。若手です。 川原がとても賑わっていました。
川原がとても賑わっていました。 伯林寺(はくりんじ)という寺の案内板が県道脇に立っていたので階段を登り小山を越えて立ち寄ってみました。十一面観音立像が安置されているらしいけれど残念ながら扉はビシッと閉じられていました。
伯林寺(はくりんじ)という寺の案内板が県道脇に立っていたので階段を登り小山を越えて立ち寄ってみました。十一面観音立像が安置されているらしいけれど残念ながら扉はビシッと閉じられていました。 県道に戻っててくてく歩き、県道をはなれて入間川を渡り、さわらびの湯はもうすぐです。
県道に戻っててくてく歩き、県道をはなれて入間川を渡り、さわらびの湯はもうすぐです。 見えてきました。旧名栗街道を歩きはじめて4時間弱。ようやくさわらびの湯に到着です。
見えてきました。旧名栗街道を歩きはじめて4時間弱。ようやくさわらびの湯に到着です。 風呂上がりの缶ビールです。乾杯! 早朝につくったわたくし製スパムおにぎらずを肴にします。
風呂上がりの缶ビールです。乾杯! 早朝につくったわたくし製スパムおにぎらずを肴にします。山の神様、地権者の皆様、きょうもありがとうございました。車道歩きはそこそこ過酷でしたがなんとか歩き通せました。ヘンなものや謎なもの、美しい花や景色に出くわすたびにエネルギー補給になりました。はてさて、次はどこを歩きましょう。また、よろしくお願いします。