今回は夕倉山尾根(ゆうぐらやまおね)を登り、三方山北尾根(さんぽうさんきたおね)を下りました。どちらもテキトーな名付けです。
夕倉山尾根は成木川と北小曽木川の中間尾根で、三方山北尾根は青梅丘陵の三方山(石神入山)から北へ北小曽木川に向かって下ってる尾根です。って書きましたが場所は下の地図のほうがはるかにわかりやすいと思います。
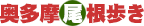
夕倉山尾根、三方山北尾根
(1/2)
| ■コース | [START]JR青梅線軍畑駅→下畑軍畑線→松ノ木通り→(45分)登り口→(30分)夕倉山尾根→381m標高点(ノボリオイゾネ)→(50分)夕倉山→372m標高点→319m標高点のちょっと手前→(1時間45分)蜆沢院の近く→三方山北尾根→(1時間30分)三方山→青梅丘陵ハイキングコース→(1時間50分)[GOAL]JR青梅線青梅駅 (7時間10分) |
| ■歩いた日 | 2024年2月17日(土) |
※赤い線が歩いた軌跡です。ただ、正確無比なものではありません。あ〜、そ〜、このあたりを歩いたんだ、程度の参考にしてください。
■[START]JJR青梅線軍畑駅→下畑軍畑線→松ノ木通り→(45分)登り口→(30分)夕倉山尾根→381m標高点(ノボリオイゾネ)→(50分)夕倉山→372m標高点→319m標高点のちょっと手前
夕倉山尾根は大中小のピークをいくつも越えながら東西に長く続く尾根です。道はしっかりしているんですがピークのたびに進行方向を確認しないと支尾根を下って期せずして終了! の憂き目にあってしまいます。夕倉山尾根の東端は想像以上の広大な採石場でした。いろいろなはたらくくるまが眼下にちっちゃく見えました。下山は地形図の破線(徒歩道)を探して南下したんですが、これがなかなか冒険チックでした。
 おはようございます。JR青梅線の軍畑駅(いくさばたえき)です。電車は奥多摩駅に向かって加速していきます。
おはようございます。JR青梅線の軍畑駅(いくさばたえき)です。電車は奥多摩駅に向かって加速していきます。 改札を出て左へ。踏切を渡って右に下り、都道193号(下畑軍畑線)をひたすらてくてくてくてく北上します。
改札を出て左へ。踏切を渡って右に下り、都道193号(下畑軍畑線)をひたすらてくてくてくてく北上します。 不動尊や地蔵尊を通過し、
不動尊や地蔵尊を通過し、 高水山への登山口に続く平溝川沿いの道を分け、
高水山への登山口に続く平溝川沿いの道を分け、 すっかり荒廃してしまった「国立奥多摩美術館」を過ぎ、
すっかり荒廃してしまった「国立奥多摩美術館」を過ぎ、 榎峠を越えます。青梅丘陵ハイキングコースの西端です。
榎峠を越えます。青梅丘陵ハイキングコースの西端です。 峠からだらだらと下り、このエリアの石灰産業の先駆けとなった佐藤さんにまつわる「佐藤塚」と
峠からだらだらと下り、このエリアの石灰産業の先駆けとなった佐藤さんにまつわる「佐藤塚」と カモシカで左折し、松ノ木通りへ。
カモシカで左折し、松ノ木通りへ。 地形図に実線(軽車道)が引かれている道ですがきっとなにかの間違いでしょう。
地形図に実線(軽車道)が引かれている道ですがきっとなにかの間違いでしょう。 落石防護網沿いはもう歩けません。山腹のかすかな踏み跡へ逃げるように登ります。
落石防護網沿いはもう歩けません。山腹のかすかな踏み跡へ逃げるように登ります。 ずいぶんしっかりした道になりました。
ずいぶんしっかりした道になりました。 荒れてはいますが道は続きます。
荒れてはいますが道は続きます。 あの稜線が夕倉山尾根です。谷地形を大きなくの字くの字で登っていきます。
あの稜線が夕倉山尾根です。谷地形を大きなくの字くの字で登っていきます。 夕倉山尾根を横切る峠に着きました。
夕倉山尾根を横切る峠に着きました。 これから歩く右手に馬頭観音が立っています。おそらく4体(石なのか像なのかはっきりしないものが1体)。年号が読めたいちばん古いものは天保2年(1831)でした。
これから歩く右手に馬頭観音が立っています。おそらく4体(石なのか像なのかはっきりしないものが1体)。年号が読めたいちばん古いものは天保2年(1831)でした。 夕倉山尾根の始まりはしっかりした尾根道です。
夕倉山尾根の始まりはしっかりした尾根道です。 ぐーっと登って標高420m圏(以降「標高」は省略)のピークです。これからいくつもいくつもピークを越えることになります。そのたびに進路チェックは必須。ここも右に進むと歩いてきた道に戻ってしまいます。
ぐーっと登って標高420m圏(以降「標高」は省略)のピークです。これからいくつもいくつもピークを越えることになります。そのたびに進路チェックは必須。ここも右に進むと歩いてきた道に戻ってしまいます。 ピークからとんがった山が見えました。採石場の音が聞こえてきます。夕倉山尾根はずーっと重機のエンジン音や低い地鳴りのような音を聞きながら歩くことになります。
ピークからとんがった山が見えました。採石場の音が聞こえてきます。夕倉山尾根はずーっと重機のエンジン音や低い地鳴りのような音を聞きながら歩くことになります。 ぐーっと登って
ぐーっと登って 細長い尾根のどこかが381mの標高点ですが、それらしい場所に「ノボリオイソネ」と書かれた山名板がありました。
細長い尾根のどこかが381mの標高点ですが、それらしい場所に「ノボリオイソネ」と書かれた山名板がありました。 標高点を過ぎてすぐの分岐はこの右のしっかりビシッとした尾根ではなく、
標高点を過ぎてすぐの分岐はこの右のしっかりビシッとした尾根ではなく、 左の雑な雰囲気のこちらが歩きたい夕倉山尾根です。油断なりません。
左の雑な雰囲気のこちらが歩きたい夕倉山尾根です。油断なりません。 すぐにすっきりした道になりました。
すぐにすっきりした道になりました。 登ってくると小さな広場みたいな平坦地に出ました。ゴッツい滑車がいくつも山に埋まりかけていました。
登ってくると小さな広場みたいな平坦地に出ました。ゴッツい滑車がいくつも山に埋まりかけていました。 正面は削り取られたようなほぼ垂直の崖です。右に回り込んで登っていくと
正面は削り取られたようなほぼ垂直の崖です。右に回り込んで登っていくと またすっきりした尾根道が復活。
またすっきりした尾根道が復活。 こんもりした茂みのてっぺんは
こんもりした茂みのてっぺんは 夕倉山の山頂でした。三等三角点があります。標高は411.17m、基準点名は北小曾木。展望はほぼゼロ。とくにすることもないので先に進みます。
夕倉山の山頂でした。三等三角点があります。標高は411.17m、基準点名は北小曾木。展望はほぼゼロ。とくにすることもないので先に進みます。 快適な尾根道です。
快適な尾根道です。 夕倉山山頂の次の380m圏のピークです。平坦でここも進路がわかりづらいです。東進を堅持。
夕倉山山頂の次の380m圏のピークです。平坦でここも進路がわかりづらいです。東進を堅持。 行く手が明るくなってきました。
行く手が明るくなってきました。 伐採地に出ました。成木街道沿いの集落や採石場が見えます。夕倉山尾根の貴重な展望地です。
伐採地に出ました。成木街道沿いの集落や採石場が見えます。夕倉山尾根の貴重な展望地です。 歩きやすそうな尾根が左や右にたくさん現れますが惑わされてはいけません。
歩きやすそうな尾根が左や右にたくさん現れますが惑わされてはいけません。 360mあたりの小ピークのT字路は左へ。
360mあたりの小ピークのT字路は左へ。 すぐに372mの標高点です。このあたりのはずです。
すぐに372mの標高点です。このあたりのはずです。 鉄塔の跡地なのか予定地だったのかなんなのか、原っぱの隅に東京電力の標石が埋まっていました。
鉄塔の跡地なのか予定地だったのかなんなのか、原っぱの隅に東京電力の標石が埋まっていました。 標高点を過ぎるとなんとなく道が荒れてきたというか歩かれていない雰囲気になってきました。
標高点を過ぎるとなんとなく道が荒れてきたというか歩かれていない雰囲気になってきました。 とっても進路がわかりづらかった場所。南(右)に下る支尾根をちょっと下ってしまいました。道がなくなったので「ヘン」と思いスマホGPSでチェック。東へ進路修正して事なきを得ました。
とっても進路がわかりづらかった場所。南(右)に下る支尾根をちょっと下ってしまいました。道がなくなったので「ヘン」と思いスマホGPSでチェック。東へ進路修正して事なきを得ました。 道に復帰したけれどやっぱり荒れ模様。
道に復帰したけれどやっぱり荒れ模様。 下ってきて
下ってきて 平坦で真っすぐな道を歩いていくと右手が明るくなってきて
平坦で真っすぐな道を歩いていくと右手が明るくなってきて 前方も明るくなってきて重機のエンジン音がすぐ近くから聞こえてきます。
前方も明るくなってきて重機のエンジン音がすぐ近くから聞こえてきます。 尾根の突端に出ました。319mの標高点を夕倉山尾根のゴールにしようと思ったんですが、
尾根の突端に出ました。319mの標高点を夕倉山尾根のゴールにしようと思ったんですが、 標高点はこのキツい傾斜の法面のどこか。これにて夕倉山尾根はおしまい、とします。とんでもない広さの採石場です。ンゴゴゴゴ、グガゴンンン、ピーピーピー、いろんな音が聞こえてきます。
標高点はこのキツい傾斜の法面のどこか。これにて夕倉山尾根はおしまい、とします。とんでもない広さの採石場です。ンゴゴゴゴ、グガゴンンン、ピーピーピー、いろんな音が聞こえてきます。コンビニで買った「クラフトボス ダブルカフェラテ」を飲み干して夕倉山尾根をはなれ、三方山北尾根をめざします。
