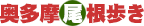
七ッ石山北尾根、登り尾根に
(2/2)
■七ッ石山→水場→七ツ石小屋→(50分)堂所→登り尾根→小袖山→(2時間10分)[GOAL]鴨沢バス停→JR青梅線奥多摩駅
登り尾根を下ったんですが、下ったというしっかりした体感はありません。いくつもピークがあって、登っては下るんですが、「これ登ってるよね」としか思えない尾根歩きが続きます。「はっはーん、だから登り尾根って名前なのかな」などと思いながら衰弱した体を持ち上げていきます。帳尻合わせは小袖山(こそでやま)を過ぎてからやってきます。短い距離でグググーッと急降下して小袖乗越にぶつかります。
ヤセ尾根があったり、バーンと広々とした尾根があったり、分岐がややこしかったり、長い尾根だけあっていろんな表情がある尾根です。
 七ッ石山の山頂から雲取山方向です。出発します。
七ッ石山の山頂から雲取山方向です。出発します。 すぐに七ッ石を通過します。切り替え画像は1935年(昭和10)に刊行された『奥多摩 それを繞る山と渓と』 (田島勝太郎著 山と渓谷社)(国立国会図書館蔵)に掲載された「七ッ石山の七ッ石」。
すぐに七ッ石を通過します。切り替え画像は1935年(昭和10)に刊行された『奥多摩 それを繞る山と渓と』 (田島勝太郎著 山と渓谷社)(国立国会図書館蔵)に掲載された「七ッ石山の七ッ石」。 七ッ石に寄り添う七ッ石神社に一礼し、
七ッ石に寄り添う七ッ石神社に一礼し、 山頂直下の水場で水を汲み、
山頂直下の水場で水を汲み、 七ツ石山小屋を通過し、
七ツ石山小屋を通過し、 1416mの標高点を過ぎたあたりを見上げながら通過し、
1416mの標高点を過ぎたあたりを見上げながら通過し、 新堂所を通過し、
新堂所を通過し、 旧堂所に到着。新堂所が整備されるまでは堂所と言えばここしかなかったと思います。旧堂所で登山道をはなれ、右の登り尾根に取付きます。
旧堂所に到着。新堂所が整備されるまでは堂所と言えばここしかなかったと思います。旧堂所で登山道をはなれ、右の登り尾根に取付きます。 こんな感じで登り尾根は始まります。
こんな感じで登り尾根は始まります。 小さなピークを越え、
小さなピークを越え、 左手奥の青い屋根の小屋を通過します。登山道近くにはブルーシートでビシッと囲まれたトイレらしきものも設営されていました。
左手奥の青い屋根の小屋を通過します。登山道近くにはブルーシートでビシッと囲まれたトイレらしきものも設営されていました。 1274mの標高点を通過します。
1274mの標高点を通過します。 道すがら。
道すがら。 1240m圏の分岐。ちょっとわかりづらいですが、右へ。まっ。ここを間違っても急降下を我慢すれば登山道に降りられるはず。
1240m圏の分岐。ちょっとわかりづらいですが、右へ。まっ。ここを間違っても急降下を我慢すれば登山道に降りられるはず。 尾根は前触れもなくヤセて急降下です。
尾根は前触れもなくヤセて急降下です。 下ってきて
下ってきて 下ります。アセビやらなんやらかんやらの灌木で歩き辛いけど面白い、
下ります。アセビやらなんやらかんやらの灌木で歩き辛いけど面白い、 そんな尾根が続き、
そんな尾根が続き、 急登というほどではないんですが、キツい登りが続き、
急登というほどではないんですが、キツい登りが続き、 尾根を下っていることを忘れてしまいます。
尾根を下っていることを忘れてしまいます。 海綿スポンジみたいなキノコ。シャキシャキしておいしそう。
海綿スポンジみたいなキノコ。シャキシャキしておいしそう。 1210m圏の分岐は左へ。
1210m圏の分岐は左へ。 また登ります。どうなってんでしょ。
また登ります。どうなってんでしょ。 1214mの標高点と思われる場所を通過します。「登り尾根 1214m」と書かれた板が木の枝に下がっていました。
1214mの標高点と思われる場所を通過します。「登り尾根 1214m」と書かれた板が木の枝に下がっていました。 久々の下りらしい下りです。
久々の下りらしい下りです。 かわいいような怖いような木を通過します。
かわいいような怖いような木を通過します。 尾根は広がり、この先で左に曲がり、
尾根は広がり、この先で左に曲がり、 快適な尾根歩きです。
快適な尾根歩きです。 1220m圏の分岐は左へ。登り尾根は分岐がかなりややこしいです。
1220m圏の分岐は左へ。登り尾根は分岐がかなりややこしいです。 快適な尾根道がずっと続きます。
快適な尾根道がずっと続きます。 ずっと続くんですが日付が入ってしまい、こちらもしばらく続きます。
ずっと続くんですが日付が入ってしまい、こちらもしばらく続きます。 正面に横たわる尾根が見えてきました。1070m圏を囲むハート形の等高線の現場です。あの尾根に登るのは避けたいです。
正面に横たわる尾根が見えてきました。1070m圏を囲むハート形の等高線の現場です。あの尾根に登るのは避けたいです。 尾根に沿うように左へ下っていき、
尾根に沿うように左へ下っていき、 テキトーなところでトラバース(山腹水平移動)して尾根に乗ります。
テキトーなところでトラバース(山腹水平移動)して尾根に乗ります。 下って左からきた尾根に乗って、てくてく歩いていくと
下って左からきた尾根に乗って、てくてく歩いていくと 小袖山の山頂です。恐ろしいほど地味な山頂ですが三等三角点があって標高は1054.08m、基準点名は小祭。
小袖山の山頂です。恐ろしいほど地味な山頂ですが三等三角点があって標高は1054.08m、基準点名は小祭。 ケーブルをまたぎます。真っ黒でしたが茶色に写っています。
ケーブルをまたぎます。真っ黒でしたが茶色に写っています。 右にカーブしながらグーッと下っていきます。
右にカーブしながらグーッと下っていきます。 やっと本気を出したのでしょうか、どんどん下ります。
やっと本気を出したのでしょうか、どんどん下ります。 910m圏の分岐は左へ。
910m圏の分岐は左へ。 倒木や枯れ枝や枯れ葉がドサドサと振りまかれたような斜面を下ります。日付に気づき、解除。
倒木や枯れ枝や枯れ葉がドサドサと振りまかれたような斜面を下ります。日付に気づき、解除。 かなりの急降下が続きます。
かなりの急降下が続きます。 790m圏の微妙な分岐は左へ。ここが最後の分岐でした。
790m圏の微妙な分岐は左へ。ここが最後の分岐でした。 小屋を通過し、擁壁上の坂道を下ると
小屋を通過し、擁壁上の坂道を下ると 小袖乗越です。これにて登り尾根はおしまいです。右の車道をゆるく登っていくと登り尾根の東面を歩く「鴨沢コース」の登山口があります。車道を下り、村営駐車場にぶつかると右の山道を下り、民家沿いのコンクリート道路を下り、
小袖乗越です。これにて登り尾根はおしまいです。右の車道をゆるく登っていくと登り尾根の東面を歩く「鴨沢コース」の登山口があります。車道を下り、村営駐車場にぶつかると右の山道を下り、民家沿いのコンクリート道路を下り、 鴨沢バス停に到着です。16時35分発のバスがやってきました。誰も乗っていないバスに高齢の男性ソロハイカーと2人で乗車。2人が左右の最前列に座ったものだから運転手を含めた3人がぎゅっと前方に固まってしまい、なんともアンバランスな雰囲気でバスは出発。寝入ったソロハイカーの熊鈴を高らかに鳴らしながらバスは快走し、小河内神社や奥多摩湖で徐々にバランスを取り戻していきました。
鴨沢バス停に到着です。16時35分発のバスがやってきました。誰も乗っていないバスに高齢の男性ソロハイカーと2人で乗車。2人が左右の最前列に座ったものだから運転手を含めた3人がぎゅっと前方に固まってしまい、なんともアンバランスな雰囲気でバスは出発。寝入ったソロハイカーの熊鈴を高らかに鳴らしながらバスは快走し、小河内神社や奥多摩湖で徐々にバランスを取り戻していきました。 途中下車したて缶ビールを購入。いったいなにがあったのでしょう。奥多摩の女(ひと)がいなくなっていました。連休初日なので遠出でしょうか。ちょっと心配です。
途中下車したて缶ビールを購入。いったいなにがあったのでしょう。奥多摩の女(ひと)がいなくなっていました。連休初日なので遠出でしょうか。ちょっと心配です。山の神様、地権者の皆様、きょうもありがとうございました。初っ端の激登に消耗させられた七ッ石山北尾根、ちっとも下らない登り尾根、それぞれ個性のある面白い尾根でした。また、よろしくお願いします。